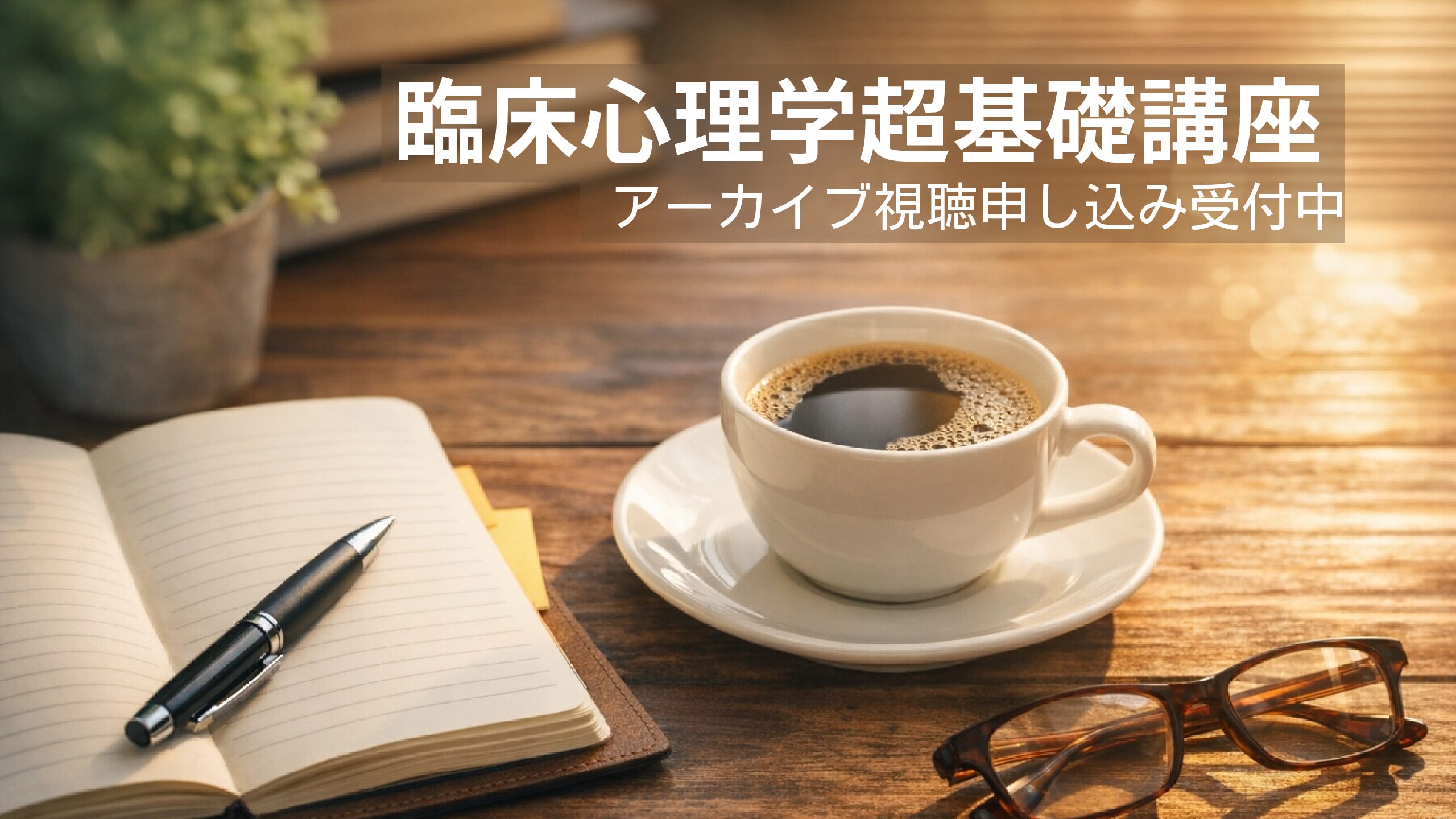心理学の知識や技術以前の臨床家としての素地とは?後編

臨床家としての素地に必要なこととは?
では、どんな素地を持っていると臨床家として活きてくるのでしょうか?ここからは、「あまり言語化されていないけれど、実は大きな差になる要素」についていくつか見ていきたいと思います。
目次
Toggle1. コミュニケーション能力
まず大切なのは、何と言っても「コミュニケーション能力」です。人と話すのが好きかどうか、対話を楽しめるかどうかというのは、意外と大きなポイントです。
「人と話すのが得意じゃないけど、心理職をしている」という方も中にはいらっしゃるでしょうし、そういう方が優秀であるケースもあります。でもやっぱり、しんどいですよね。臨床の現場では、日々のやり取りのなかに「人と関わることの喜び」を見出せることが、やっぱり大事なんだと思います。
話しすぎてしまったなと自分を振り返れるか、相手への配慮ができるか。自分の話を楽しむことと、相手との関係性に目を配ることのバランス感覚。そういった「解像度の高い」コミュニケーション感覚が臨床家として活きてきます。
また、コミュニケーション能力には「タイプ」があります。ただ相手を圧倒するような交渉型のコミュ力が役に立つ場面もありますが、臨床の現場で必要とされるのは、むしろ「相手の話を受け取って関係性を築いていく」力です。相手の反応に気づき、必要なら立ち止まり、関係性の中で自分のあり方を調整できること。これがカウンセラーに求められるコミュ力の質だと思います。
2. 信頼を前提とした人間観
もう一つ、大切なのは「人を信頼する姿勢」をどこまで持てているかということです。
どんな人でも、基本的には成長していける力を持っている、という世界観。人のなかには、明るい側面もあれば、暗い側面もある。その両方を見ながら、あるいは引き受けながら、まるごと関わろうとする姿勢。
臨床においては、「どちらかだけを見ようとする」姿勢が時に相手を追い詰めてしまうことがあります。ときには相手の苦しさや怒り、不信感の表現に耐えることも必要です。太陽のようなあたたかさを持ちつつ、しかし時には静かに陰の部分を受けとめられるような、そんな人間観があると、関係性の中でのバランスを取る助けになります。
そしてその土台にあるのが、「人間そのものへの信頼」なのだと思います。
3. 論理的思考と柔軟性のバランス
もうひとつ、臨床家として重要なのが「論理的思考力と柔軟性のバランス」です。
ここで言う論理的思考とは、「ある前提をもとにして、矛盾のない方法で結論を導く力」だけではありません。もっと実践的に言えば、「混沌とした状況の中に、かすかな筋道を見出す力」だと思います。
臨床では、たとえば「母親との関係がこうだったからこうなった」といった単純な図式化では済まされないことがほとんどです。過度な一般化や思い込みに陥ってしまうと、本人の可能性を閉ざしてしまう危険すらあります。
そういう中で、「この人はどこに向かいたいのか」「何が今、足を引っ張っているのか」「この場面において、何がリソースになり得るのか」といった問いを立て、仮説を立て、検証し、時には手放して再考する。そんな、仮説生成と検証の往復運動ができる思考力が臨床家には必要です。
また、形式に囚われすぎると、目の前のクライアントを見失うこともあります。エル字型の座り方、オウム返し、沈黙の活用など、形式はあくまで手段であり、目の前の関係のなかで何が起きているかを見つめ直す姿勢が、臨床の質を支えます。
こうした「論理的思考」と「柔軟性」を併せ持つことが、臨床家としての一つの柱になるのではないでしょうか。
4. 解像度の高い内省力と学習姿勢
臨床家として長くやっていく上で欠かせないのが、「自分自身を振り返り、問い直していける力」です。
これは、単なる反省や自己批判とは異なり、「今の自分の状態や行動、思考、感情をできるだけ細やかに捉えてみる」という態度のことです。
「あの場面で、なぜ自分はあんな反応をしたんだろう?」 「クライアントのこの言葉に、なぜこんなにも引っかかっているのだろう?」
そうした問いを丁寧に取り扱うことができる人は、臨床の現場でより深い関係性を築きやすくなります。
また、それと同時に「学び続ける姿勢」もとても大切です。心理臨床は経験がものを言う世界である一方で、経験だけでは行き詰まってしまうことも多々あります。
自分が知らないこと、見落としている視点があるかもしれないという前提で動けるかどうか。他者の意見を取り入れ、理論を学び直し、スーパービジョンやコンサルテーションを受け続けることができるかどうか。
このような「内省力」と「学習姿勢」が、臨床家としての成長を支えていくのだと思います。
5. 感覚と論理の往復運動
臨床の現場では、時に「理屈では説明しきれないこと」に出会います。目の前のクライアントの微細な表情、空気感、間(ま)……そうしたものを「感じ取る」力も、私たちには求められています。
けれど、それを感覚だけで終わらせるのではなく、あとから「なぜそう感じたのか」「その感覚はどこから来るのか」を言語化していく。それが臨床家としての「感覚と論理の往復運動」です。
この往復があることで、臨床はただの感覚的な寄り添いではなく、構造化された「対話」になります。逆に、理屈だけで動いてしまうと、関係性の中で起きている大切なことを取りこぼしてしまう。
「感じる」→「言葉にする」→「考え直す」→「また感じる」
こうしたサイクルを、無理なく自然に繰り返していけるような在り方を目指したいものです。
6. 他者との関係性の中で育つ力
心理臨床という営みは、つねに「他者との関係」のなかで進行します。クライアントとの関係性はもちろんのこと、同僚や上司、スーパーバイザー、他職種との協働関係など、「一人で完結する仕事」ではないという点を見落としてはならないと思います。
ここで大切なのは、単に「協調性がある」や「うまくやっていける」ということにとどまらず、「関係性のなかで自分をどう位置づけていくか」という姿勢そのものです。
たとえば、ある種の臨床的センスは、先輩や仲間の姿を見て学ぶことがあります。あるいは、スーパービジョンの中でのちょっとしたやりとりから、「ああ、こういう見方もできるんだ」と発見することもあるでしょう。
そうした関係性の中で、自分の考えが少しずつ耕されていく。時には対話によって自分の限界が照らされ、時には誰かの眼差しによって、自分の強みに気づくこともあります。
「対話によって自己が育っていくプロセス」──この実感を持てるかどうかは、臨床家として非常に大きな違いを生みます。
また、クライアントとの関係性もまた、臨床家自身を育ててくれます。
「ああ、この方とのやり取りの中で、こんな視点が生まれた」 「この方の語りを聴くうちに、自分の中の価値観が揺れ動いた」
そうした一つひとつの関係性のなかで、自分という臨床家の輪郭が、少しずつ少しずつ浮かび上がってくるのだと思います。
7. 臨床家の“好き”や“向き不向き”を大切にする
心理臨床の世界には、本当に多種多様なフィールドが広がっています。教育、医療、産業、福祉、司法……それぞれに違った文化があり、求められるスキルや役割も大きく異なります。
そんな中で、自分の「好き」や「向いていること」「なんだかしっくりくる感覚」を大切にしていくということは、とても重要です。
もちろん、「どの現場でもある程度のことはできるように努力する」という姿勢も必要ですが、長く臨床の仕事を続けていくには、自分の“心が喜ぶ方向”に正直であることも大きな資源になります。
たとえば──
-
子どもと関わるのが好きで、つい自然に笑ってしまう。
-
病院のように構造化された場で、じっくり対話を積み重ねるのが得意。
-
人前で話すのが好きで、研修や啓発活動にやりがいを感じる。
-
制度の中で支援をつなぐコーディネート的役割に魅力を感じる。
こうした「好き」や「得意」があるからこそ、その現場での臨床が自然と深まっていくことが多いのです。
一方で、「この領域は、どうにも力が入らない」「気持ちが疲弊してしまう」という場面も、臨床家であれば誰しもあると思います。それを無理に押し殺して頑張り続けることは、燃え尽きや離職のリスクにもつながります。
だからこそ、自分の“向き不向き”を素直に見つめ、それに合わせたフィールドで力を発揮していくという視点が大切です。
「好き」「得意」「しっくりくる」という感覚もまた、大切なリソースなのです。
8. 基礎と応用をつなぐ視点
大学や大学院で学ぶ「基礎」は、実践を支える大切な土台です。けれども、その基礎をそのまま現場に適用しようとすると、うまくいかないことも多くあります。
なぜなら、現場ではいつも「想定外」のことが起こるからです。
大切なのは、基礎的な理論や技法を、目の前の現実にどう編み直すか。そのプロセスにおいて、「どこまでが守るべき基礎で、どこからが応用なのか」という線引きを、自分なりに考えていける姿勢です。
これは、一見すると「型を崩す」ことにも思えるかもしれませんが、実は「型を深く理解しているからこそ崩せる」という営みでもあります。
つまり、理論や技法の背景にある「人間理解」や「臨床観」といった、より根本の部分に立ち返りながら、現場での応用を考えていく。これができると、ただのアレンジではなく、「意味のある工夫」が可能になります。
臨床家として、「知っている」ことと「使える」ことのあいだを行き来しながら、日々の実践の中で“自分なりの心理臨床”を形づくっていく──そんな学びの視点が、今、求められているように思います。
9. 違和感を手がかりにできる力
心理臨床の現場では、必ずしも「分かりやすい困りごと」だけがテーマになるわけではありません。むしろ、「なんとなく引っかかる」「ちょっと気になる」といった、“違和感”が、後に重要な意味を持つことが多くあります。
この違和感を丁寧に扱えるかどうか。つまり、「自分が何に反応しているのか」「何がズレていると感じるのか」を無視せずに探っていける力は、臨床家として非常に大切な力のひとつです。
違和感は、ともすれば「自分の問題」として片付けてしまいがちです。でも、違和感には、目の前の関係性や力動、あるいはその人のストーリーに触れるためのヒントが詰まっていることがある。
その違和感を丁寧にたどりながら、「今ここで、何が起きているのか」「自分の内側で何が反応しているのか」を見つめる視点を持ち続けること。これは、専門的なスーパービジョンを受ける際にも大きなテーマになりますし、同時に、臨床家としての自律性を育てるプロセスでもあります。
「なんか引っかかる」という違和感の種を、臨床的な問いに変えていけるかどうか。そこに、臨床家としての深まりがあるように思います。
まとめ 臨床家の成長のために
論理を超えた論理、なんていうと「何の話?」と思われるかもしれません。でも、僕が言いたいのは、混沌とした状況の中でも機能するような“論理的思考”があるということなんです。もちろん「それも論理的思考じゃないの?」ってツッコミたくなる人もいるでしょう。けれど、そういう矛盾を抱えたところにこそ、僕らの仕事の面白さがあるんじゃないかなと思うんです。
だからやっぱり、ロジカルな思考ができるに越したことはないんですよね。僕は「感覚派」とよく言われますし、実際そうなんですけど、でも、感覚的にやっていることに、あとからでも理屈をつけていくっていう作業はすごく大事だと思っています。
それは心理学の理論に限らず、自分たちの知らないところでもすでに誰かが言語化していたりするわけです。自分の中で「これは発見だ!」と思っても、実は誰かがすでに言っていた、なんてこともしょっちゅうあります。でもそれって、どこかの誰かの言葉や考えが、時を超えて自分に伝わってきたっていうことでもありますよね。
つまり、僕らはすでに臨床心理学という大きな流れの中に身を置いているわけで、その中で泳ぎながら、自分なりの理屈を見つけていったり、「あ、これってあの理論とつながるんだな」と学びながら進んでいく。それが僕らの仕事なんじゃないかと思うんです。
だからこそ、「意識化して知っていること」と「意識化していないけど知っていること」が、日々の臨床の中でスパークして積み上がっていく——それが成長なんじゃないかなと感じています。
臨床家に必要なものって、本当にいろいろあると思います。たとえば、倫理的な姿勢、自我の安定性、心理学的な知識、身体的な健康……それに、自分が向いている領域って自然とあると思うんです。子どもと相性がいい人もいれば、思春期が苦手な人、高齢者と過ごすのが落ち着く人もいる。みんな、自分の持っている“人間としてのパラメーター”で補い合いながら、少しずつ“解像度”を上げていく——そういう風にして臨床をやっているんじゃないかなと。
だから、自分の臨床の中で「基礎のさらに手前のところ、発想や視点の切り替えについてもう少し成長したいな」と感じている方には、ぜひ『臨床超基礎講座』にご参加いただけたらと思います。
学校や通常の研修では、どうしても“その先”の内容にフォーカスされがちです。でも、この講座は、その“手前”の部分——基礎の基礎を、丁寧に扱う研修です。とはいえ、受けてみて「全然手前じゃないじゃん!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが……(そのときは、そっと苦情ください)。
講座は4月から始まります。現在の予定では、毎月第3金曜日の21時〜23時に開催予定です。
-
第1回(4月18日):傾聴
→ 傾聴は知っているだけではなく、「できる」こととの間に大きな距離があります。解像度を一緒に上げていきましょう。 -
第2回(5月16日):治療構造
→ “治療の枠”をどう考えるかについて深掘りします(※変更の可能性あり)。 -
第3回(6月20日):見立て
→ 「そんな見立てもアリなの?」と思ってもらえるような、面白い内容になると思います。 -
第4回(7月18日):共感
→ 共感は奥が深くて、踏み込んでいくととても面白いテーマです。 -
第5回(8月15日・お盆):理解を伝える(予定)
→ 言い方ひとつでクライアントの反応が大きく変わります。ここでは“抵抗処理”の技法にも触れられたらと思っています。 -
第6回(9月19日):まとめと質疑応答
→ 全体の振り返りと、皆さんの疑問にじっくりお答えします。
そして、後半は10月17日から始まる『解決志向・超基礎講座』。どの理論的背景を持つ人にも役立つ内容を予定しています。
いずれの講座も、参加者の皆さんや、参加されない方の声も取り入れながら、今まさに作っているところです。「こういうところに困っている」といった声に応じて、内容を調整していきたいと考えています。
▼ 詳細・お申し込みはこちらから: https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854

また、講座準備の一環として、「カウンセリングに関する基礎的な困りごと(傾聴・関係づくり・治療構造など)」に関する情報を集めています。
実際の現場で感じていること、疑問に思っていることを、以下のアンケートフォームからお寄せください。
皆さまのお声をもとに、より実践的で役に立つ講座にしていきたいと考えています。
▼ アンケートご協力のお願い: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RJ60vZgjrulKrvRrRF5VqnCZnZlFzgf6wBByqvrrBVj1gA/viewform?usp=sharing
それでは、またお会いできるのを楽しみにしています。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!