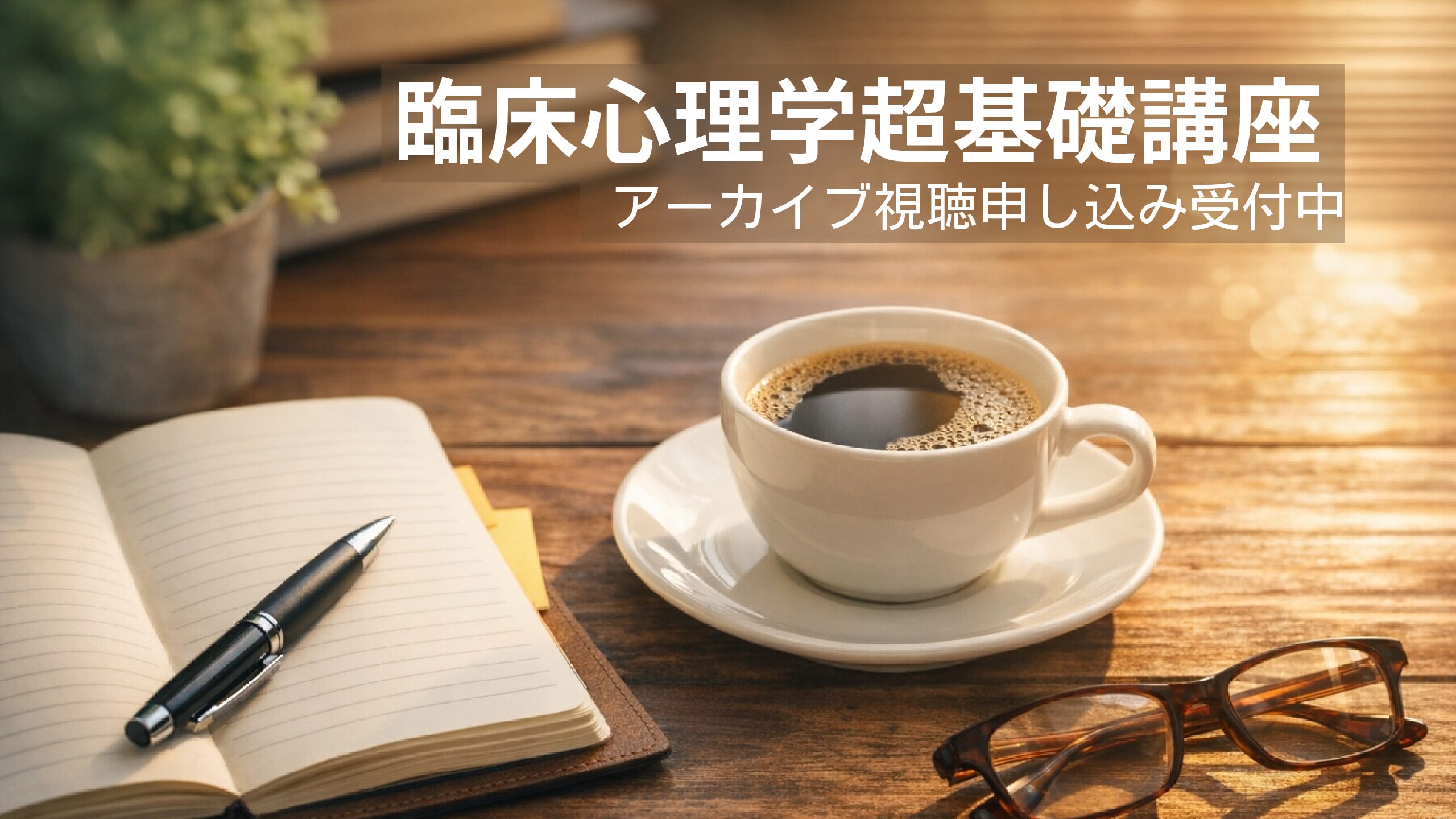臨床心理学基礎実習の備忘録―「関わり行動」と身体の気づきについて―

大学院の実習授業で「関わり行動(relating behavior)」をテーマにした実習を行いました。
学生たちは、ノンバーバル(非言語)的なコミュニケーション──たとえば姿勢や目線の向け方──が相手にどんな印象を与えるのか、実際に体験しながら考えていました。
「姿勢を少し変えるだけで、相手の反応が違う気がする」
「目を見すぎても圧があるし、見ないと関心がないように思われる…」
そんなふうに、身体の使い方を通して自分と相手の関係性を探る姿勢が印象的でした。
自分の体に現れる「こころ」の状態
授業の中では「ミラーリング」という概念にも触れました。
相手の身体の動きに合わせることでラポール(信頼関係)を築く、という技法として知られています。
ただし、これを「わざとやっている」と相手に気づかれたら、むしろ不信感を生むこともあります。
大切なのは、自分がいまどんな姿勢をとっているのかを意識し、その背景にある自分の心の状態を感じ取ることです。
たとえば──
身体が前のめりになっていたら:「あ、今けっこう相手にコミットしてるな」 腕を組んでいたら:「少し防衛的になってるかもしれない」 胸が苦しい感じがしたら:「緊張しているのかもしれない」
そんなふうに、自分の体を“心のセンサー”としてモニタリングしていく。
それはまさに「逆転移を身体で感じる」ような作業です。
同調しすぎないための「間」
また、面接中に「相手と同調しすぎている」と気づく瞬間があります。
たとえば相手が早口になると、こちらもどんどんペースが上がっていく。
そんな時は、少し呼吸を整えて**「間」をつくる**のが大切です。
「ちょっと私、今すごい勢いで話してしまいましたね。このペースで大丈夫ですか?」
こんなふうに一度差し戻すことで、お互いに呼吸を取り戻すことができます。
臨床の現場では、こうした“阿吽の呼吸”のような間合いが関係の質を左右することも少なくありません。
「自然さ」と「専門性」のあいだで
「自然にふるまうのが一番いい」とよく言われます。
しかし、その“自然さ”が相手にとって失礼だったり、不安を招くものであれば、臨床的には適切とは言えません。
ですから、いちど自分の関わり方を意識的に分解して点検することが必要です。
この姿勢はどう見えているだろう? この間の取り方は適切だったか?
そうやって検討したうえで、もう一度「素直な自分」に戻っていく。
この往復運動こそが、臨床心理の難しさであり、同時に面白さでもあると思います。
おわりに
身体の使い方や姿勢、呼吸、目線──それらはすべて、臨床家の“こころのあり方”を映し出す鏡です。
そして、その鏡を通して相手との関係を確かめ直す作業こそ、臨床心理学の実習で学ぶべき「基礎」なのだと思います。
自分の体を通して、今ここで何が起きているかに気づく。それが、関わり行動を理解する第一歩かもしれません。
さらなる学びを求めている方に
臨床心理学超基礎講座 1DAYワークショップのご案内
10月開講 〜スクールカウンセラーのための〜 解決志向超基礎講座
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!