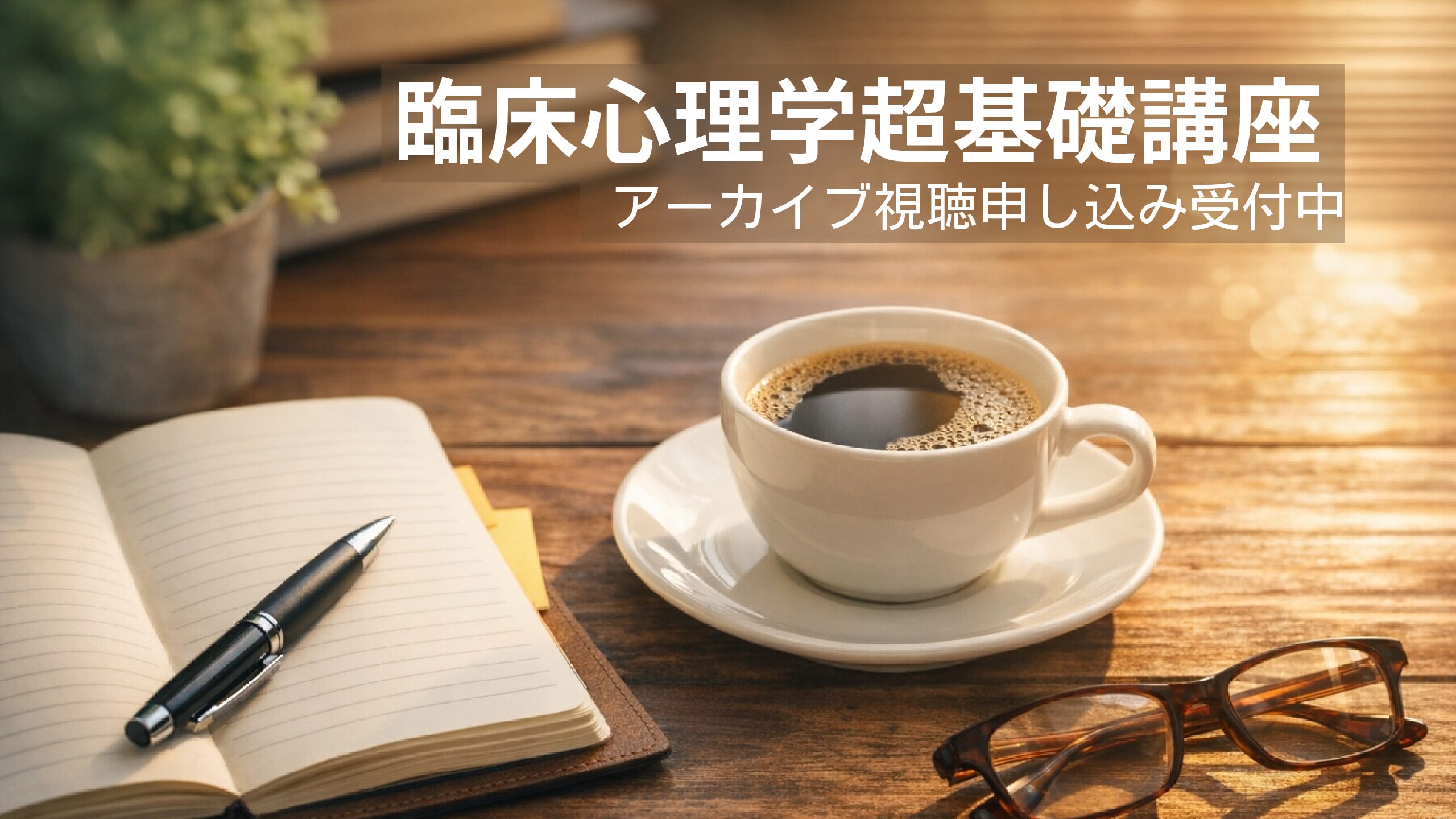【臨床心理学超基礎講座】なぜ「構造」の違いを知る必要があるのか?その1:様々な構造

臨床心理学超基礎講座#2:「治療構造と転移」にて扱われた内容を一部紹介させていただけたらと思います。
目次
Toggle代表的な場面で「構造」を比較してみる
相談の現場と一口に言っても本当にいろんな形があります。
開業心理士としての自由診療から、病院内の医療構造の中での面接、さらには学校やSNSなどを通じた相談まで。
それぞれのフィールドには、そのフィールドならではの「構造」「目的」「求められる支援スタイル」があります。
それを知っておくことは、支援者にとっても、相談を受ける側にとっても、とても大切なことだと私は思っています。
今回は「治療構造」について、実際の現場でどう異なるのか――その違いを少し整理してみたいと思います。
◆ なぜ「構造」の違いを知る必要があるのか?

-
- 私設相談室の心理士
- 医師と併設で動くクリニック
- 医療に組み込まれた病院内の面接
- 教育現場に入っていくスクールカウンセラー
- 匿名性の高いSNSや電話相談
こうした様々な「場」には、それぞれ異なる構造、目的、そして「求められる支援スタイル」があります。
この違いを知っておくことで、私たちの支援の選択やスタンスも、より的確になっていくはずです。
■ 私設相談室
私設相談室というスタイルでは、構造を比較的自由に設計できます。
ただし、だからこそ 「ここでは何をする場なのか?」 を明確に言語化しておく必要があります。
時間・料金・方針・目標――こうした“枠”をちゃんと提示し、クライアントと合意して進めることが求められます。
構造の自由さが裏目に出ると、「何をする場かわからない」「ずるずる続いている」なんてことにもなりかねません。
■ 病院内(病棟・外来)
病院内で行うカウンセリングは、医療構造の一部としての相談になります。
主治医との連携や、治療方針の共有が前提になりますし、
ときには医療チームの一員として、チーム会議に参加するような役割もあるかもしれません。
この場では、「心理支援」と「治療行為」が一体となる形で進むことが多く、
枠組みはしっかりしている一方で、「医療チームの一員としての心理士」としての自覚と工夫が求められます。
■ クリニック併設
クリニックの中に併設されている心理相談室は、病院ほど厳密な医療構造ではない一方で、
医師との連携が求められる半医療的なフィールドと言えます。
医師の診察や処方とのバランスを考慮しながら、心理的なアプローチを展開していく。
そうした「中間的な位置づけ」ゆえの柔軟性と慎重さの両方が求められる構造です。
■ スクールカウンセラー
スクールカウンセラーは、公教育という制度の中で提供される心理支援です。
そのため「構造」は、ある意味で一番“揺れやすい”かもしれません。
- 相談室が物理的にどこにあるか
- 学校内でのカウンセラーの立ち位置
- 担任や管理職との関係
- 来室の方法や時間設定
- 面接の記録や共有の扱い方
…など、状況に応じて毎回判断が求められることばかりです。
その場その場で「この子にとって、この環境で、今できるベストな支援は何か?」と考えることが多く、
調整力・柔軟性・即応性が試される場だと言えるでしょう。
■ 電話・SNS相談
ここでは、さらに即時性と匿名性の高い相談の場が登場します。
電話相談やSNS相談は、構造の設定が非常に難しいフィールドです。
- 匿名
- 即時的、短時間あるいは長時間になる場合も
- 相談者は生活の場面にいながら相談している
- 単発が多いがリピーターがほとんどだったりすることも
- 危機介入の可能性
こうした特徴があるため、「構造を設計する」というよりも、**短時間で構造を“見立てて”、必要に応じて“即座に構造をつくる”**必要が出てきます。
また、支援の打ち切りや他機関へのリファーなども含め、危機的判断を迫られる場面が非常に多いフィールドです。
◆ 構造は「見えないけれど、確かにあるもの」
ここまで5つの代表的な相談場面を見てきました。
どの場にも共通するのは、「構造とは、ただのルールや枠ではない」ということです。
構造とは、支援を安全に、効果的に進めるための土台であり、
ときにはその人自身の変化を映し出す鏡にもなるものです。
私たちが日々向き合う相談の現場には、それぞれに違う背景・制度・期待があります。
そこにどう構造を敷き、どうその人に合った関係性を築いていくか。
この“構造を見立てる感覚”こそ、支援者としてのセンスが磨かれるところなのかもしれません。
もしこのテーマに興味を持ってくださった方がいれば、
それぞれの現場で「自分はどんな構造で支援しているだろう?」と立ち止まってみてもらえると、
また少し臨床の解像度が上がるかもしれません。
◆ 研修のご案内
治療構造についてさらに深く学びたい方は、以下の研修にご参加ください。
臨床心理学超基礎講座#1:「傾聴からはじめよう」
臨床心理学超基礎講座#2:「治療構造と転移」
(いずれもアーカイブ視聴が可能です)
次回#3「見立て」2025年6月20日21:00~23:00(その後に自由参加のアフターミーティングあり)に行われます。
詳細・お申し込みはこちらから:
https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854
皆さまのご参加をお待ちしております。

オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!