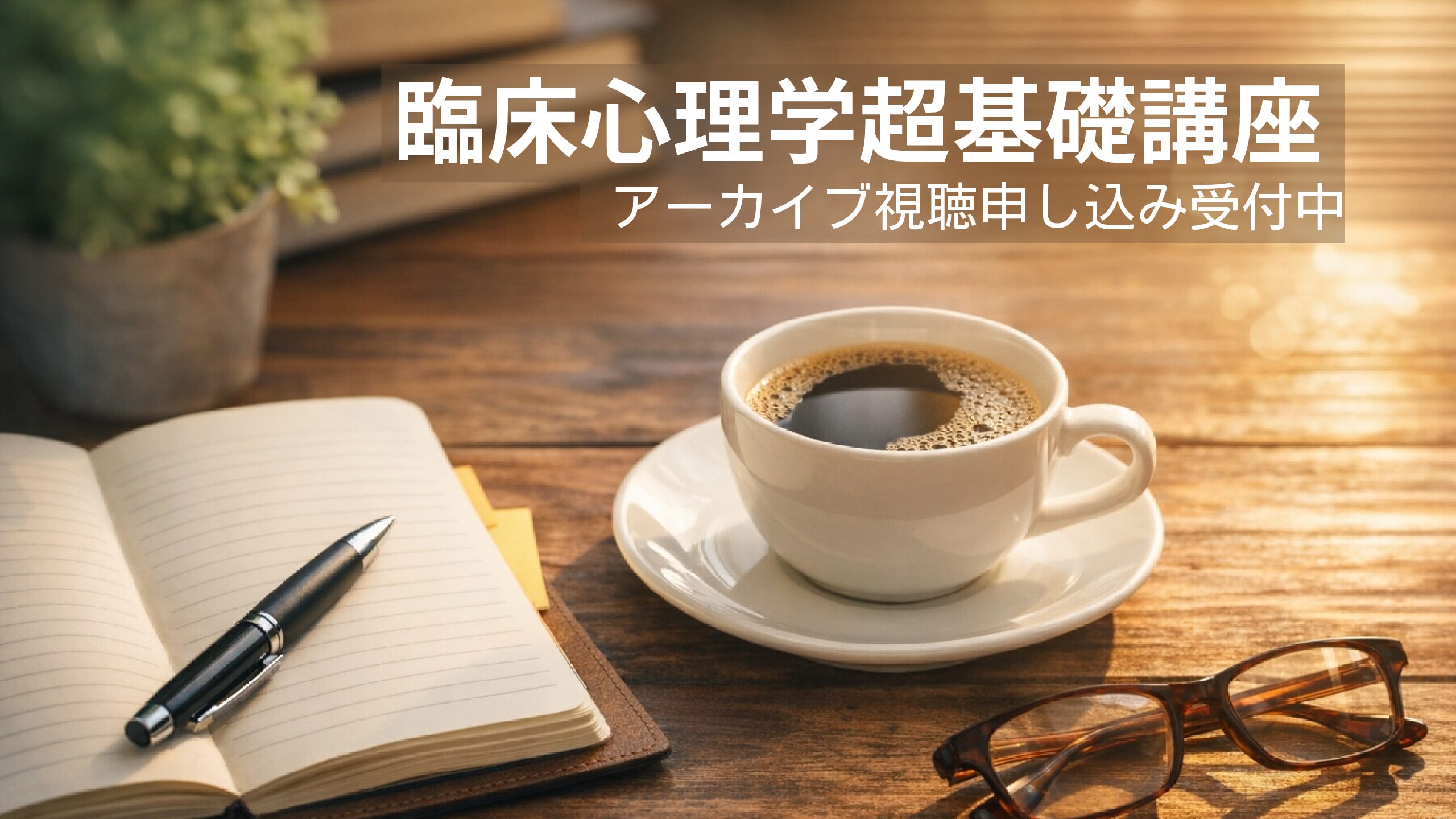【動画解説】高校生の不登校、子どもを追い詰めない、留年リミットの乗り越え方【対談:掛井臨床心理士】

高校生の不登校 – 注意点と対応策
はじめに
月に一度、スペース海の不登校チャンネルで新田恒夫先生と不登校についての対談をさせていただいています。
最近は、新田先生の仮想事例への対応についてあれこれ語っております。
以下の動画で話した内容を編集してブログに書かせていただきました。
高校生の不登校は、小中学生の不登校とは異なる特徴があります。単位制の影響、進路選択のプレッシャー、そして過去の傷つきが蓄積していることが要因となりやすいです。本記事では、高校生の不登校の特徴、対応策、親ができることについて詳しく解説します。
1. 高校生の不登校の特徴
目次
Toggle1.1 「出席日数」ではなく「単位」の問題
高校では、出席日数だけでなく 「単位取得」 が卒業の条件になります。単位を取得できなければ留年や退学の可能性が出てくるため、単なる「行きたくない」という感情では済まない現実的な問題となります。
対応策:
- 学校に確認し、「あと何回休めるか」 を早めに把握する。
- 単位を落とさないための戦略を立てる。
- 「このままだと留年になる」と後になって気づくのではなく、本人と情報を共有する ことが重要。
1.2 カウンセリングが成立しやすい
高校生は自己理解が進んでおり、自分の悩みを整理し、言葉で表現できる力が育っています。そのため、カウンセリングが機能しやすい年代です。
不登校の発達段階別の特徴:
- 小学生の不登校:環境調整が重要。保護者や先生が子どもにとって安心できる環境を作ることが鍵。
- 中学生の不登校:大人の影響を受けたくない時期。自己主張が強くなり、言葉によるやりとりが難しくなることも。
- 高校生の不登校:カウンセリングが成立しやすく、自分の気持ちを話せる機会があると回復につながりやすい。
対応策:
- 学校のスクールカウンセラーや専門家とつながる。
- 子どもが話したくなるタイミングを待ち、無理に話させない。
- 家族以外の信頼できる大人との関係を作る。
1.3 「累積した傷つき」が影響する
高校生の不登校は、過去の傷つきが積み重なっていることが多いです。
不登校の要因が蓄積するプロセス:
- 小学校:環境のミスマッチ(先生やクラスの雰囲気)が原因。
- 中学校:人間関係や成績へのプレッシャーが加わる。
- 高校:過去の傷つきが積み重なり、自己評価の低下が顕著になる。
このように、高校生の不登校は 「今の問題だけではなく、過去の経験を整理すること」 が大切です。
対応策:
- 過去の傷つきを振り返り、「なんとか耐えてきたこと」 をねぎらい、「耐えるために取り組んできたことや、役に立った資源」 について引き出し、肯定的に言及する。
- 「今の問題だけ」ではなく、「これまでの生きづらさ」も考慮する。
2. 高校生の不登校対応の具体策
2.1 出席日数のリミットを共有し、戦略的に考える
「あと〇日休める」というリミットがある場合、早めに本人と情報を共有 し、計画的に進めることが大切です。
親のよくある悩み:「学校から『あと30日は休める』と言われても、子どもが全く動かない…。」
対応策:
- 子ども自身が選べることが重要ではあるが、「どうする?」と決めさせるのは子供にとっては非常にきつい体験で追い詰められたように感じるのでその配慮が必要。
- 親が焦らず、フラットに選択肢を提示する。親の顔色を見ないで決められるところまで来ていたら大分良い状態。多くの子供は親が何を望んでるかを大事にして選びがち。そうなると自分で決めたことにならない。
- 子どもが安心して考えられる環境を整える。例えば「もし○日までに選べなければこれこれこういう方向で先生とは話しておくから」といったように、選ばないことも選択したという形にしておく等。
2.2 タイムリミットが切れても「大丈夫」と伝える
リミットに向かって子供も親も、人生の重要な局面ということで、非常に気持ちが追い詰められ、通常ではないコミュニケーションをしてしまいがちです。「リミットを迎えたら終わりではない」と伝えることで、子どもが気持ちを楽に持てますし、親自身がそう思えることで、うっかり強圧的なコミュニケーションをとってしまうことを避けることができます。
親のよくある不安:「このままだと卒業できないかも…。」
対応策:
- 「卒業しなくても、道はある」 ことを伝える。
- 通信制、フリースクール、別の進路を考える。
- 焦らず、「今できること」を考える。
2.3 「焦ると動けない」ことを理解する
不登校の子どもは、プレッシャーをかけられると逆に動けなくなります。
親のよくある失敗:「早く行かないと大変なことになるよ!」→これは本当にあるあるなのですが、こんなこと言われたら子供は余計に動けなくなりますよね。みんな頭ではわかっているのに、親自身が追い詰められているので強圧コミュニケーションを図ってしまいます。
対応策:
- 「行きなさい」ではなく、「どうしたい?」「行かなかったとしてもその後どんな感じでいきたい?」とフラットに問いかける。
- 「今学校に行かなくても、道はある」ことを、親自身がそう思えることころまで考え、本音で伝える。
- プレッシャーをかけるより、「安心感を持たせる」ことを優先する。
3. 不登校対応の選択肢
3.1 通信制・フリースクールの活用
通信制高校のメリット:
- 自分のペースで学べる。
- 登校日が少なく、無理なく学習できる。
- 専門分野(IT、デザインなど)に強い学校もある。
フリースクールのメリット:
- 多様な学びのスタイルがある。
- 関与の仕方をある程度自分で選べるので人間関係のリハビリができる。
- 全日制の高校とは違うタイプの居場所が見つかる可能性がある。
3.2 休学・留年という選択肢もある
ケースバイケースですが「一度立ち止まる」ことが、結果的に良い方向に進む例もあります。
休学・留年のメリット:
- 心と体の回復に時間を使える。
- 自分のペースで、学校と関係のない課題に主体的に取り組めえる可能性がある。
- 無理をしないことで、将来の可能性が広がる。
4. 親ができること
- 焦らず、安心できる環境を作る。
- 子どもに「選択肢」を提示する。
- 無理に学校の話をしない。
- 親自身が相談できる場を持つ。
まとめ
高校生の不登校対応は、プレッシャーをかけるのではなく、安心できる環境を作ることが重要です。「卒業しなくても道はある」 という考え方を持つのは難しいことですが、ここの発想の持ち方が、子供に大きな影響を与えます。長期的な視点で子どもの成長を見守ることが、逆に現状をひっくり返す力になることがあります。親が「もうこれでOK、無理をしないで安心で行こう!」と思った瞬間に、子供の主体性が動き出して、思いもよらぬ結末になることはよくあります。追い詰められそうな時ほど、まずは安心と関係づくりからのスタートが重要です。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!