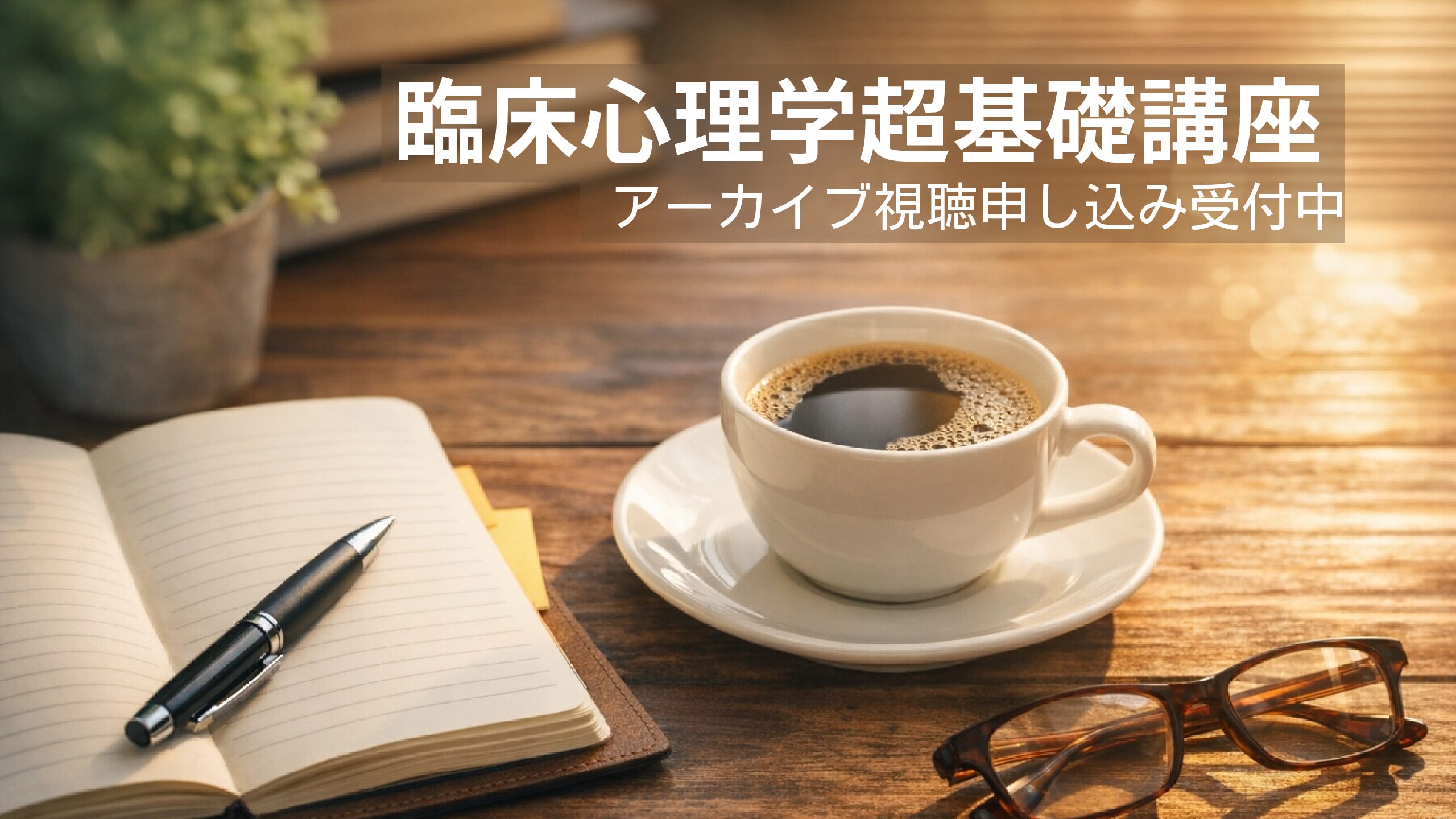保護者面接を協働的に行うために ― 相互コンサルテーションという視点

目次
Toggle相互コンサルテーション→協働
保護者面接を「専門家としてアドバイスをする場」ではなく、「一緒に考え、支え合う場」として捉えることができたらどうでしょうか? それは、いわば “相互コンサルテーション”=協働のかたち かもしれません。
「どうしたらこの子をよりよく支えられるか?」―― そんな問いを、スクールカウンセラー(SC)と保護者がそれぞれの立場から持ち寄り、意見を交わしながら一緒に考える。このスタンスを大切にすることで、面接の時間はより実りあるものになっていきます。
では、どうすれば保護者との面接を 「相談を受ける場」ではなく、「協働の場」にできるのか?
そのためのちょっとした工夫について、考えてみたいと思います。
1. 保護者面接を協働的にするための準備
仮説を持って面接に臨む
面接の場では、ただ「お話を聞かせてください」と始めるよりも、 あらかじめ仮説を立てておく ことで、対話が深まります。
たとえば…
- お子さんは、もしかすると環境の変化にストレスを感じているかもしれない
- もしかすると、保護者の方ご自身も「この相談をどう受け止めればいいのか」と戸惑っているかもしれない
- そもそも「学校に来ること自体」に負担を感じているのではないか
こうした仮説を持っていることで、「いま何について話すのが大切か?」の方向性が見えやすくなります。
2. 面接のはじまり ― 労いと感謝を伝える
仮に「学校に来ること自体が負担かもしれない」という仮説を立てた場合、それでも足を運んでくださったことに 感謝の気持ちを持つのはごく自然なこと ですよね。
「今日はお時間を作っていただき、ありがとうございます。」
「お忙しいなか、お子さんのことを一緒に考える時間をいただけて嬉しいです。」
そんな言葉が自然と出てくるのではないでしょうか。
形式的な「労い」ではなく、「この場に来てもらえたこと」に本当に感謝できると、そこからは対等な対話が生まれやすくなります。
3. 面接の中盤 ― 保護者を“専門家”として迎える
保護者面接を協働的にするためには、「情報を受け取る側」と「伝える側」という関係ではなく、 「お互いの知っていることを持ち寄って一緒に考える」 という姿勢が大切です。
「お母さん(お父さん)が一番お子さんのことをよくご存じだと思います。」
「学校で見えている姿と、ご家庭での様子が違うかもしれませんね。どんなことに気づかれていますか?」
こうした問いかけをすることで、保護者も「自分の視点が尊重されている」と感じやすくなります。
「相談に来たらアドバイスをもらうもの」と思っている方も多いので、「一緒に考えたい」というスタンスを伝えることも大事ですね。
4. 面接の終わり ― 協働を続けるために
保護者との面談が「話して終わり」にならないように、 「次の一歩」を一緒に考える のも大切なポイントです。
「今日お話ししたことをふまえて、学校ではこういうサポートができるか考えてみますね。」
「ご家庭で試してみたいことがあれば、お聞かせください。」
「また状況を見ながら、連絡を取り合えたらと思います。」
「また話せる」「一緒に考え続けられる」―― そう思ってもらえる面接になると、次回の面談もスムーズになります。
5. “相互コンサルテーション”としての保護者面接
「相互コンサルテーション」と聞くと、専門職同士の話し合いのように思えるかもしれませんが、実は 「それぞれの視点を持ち寄って、一緒に考えること」= 協働そのもの です。
- 学校での姿、保護者から見た家庭での姿
- 子どもの気持ち、大人の関わり方
- できること、できないこと
こうした視点を共有しながら、「どうしたらこの子をよりよく支えられるか?」を共に探る時間。
それが、「協働的な保護者面接」 の在り方なのかもしれません。
少しずつ、できるところから。
一緒に考える面接をつくっていきたいですね。
スクールカウンセラー向け研修情報
https://pro.form-mailer.jp/lp/cfc078e1282995
https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!