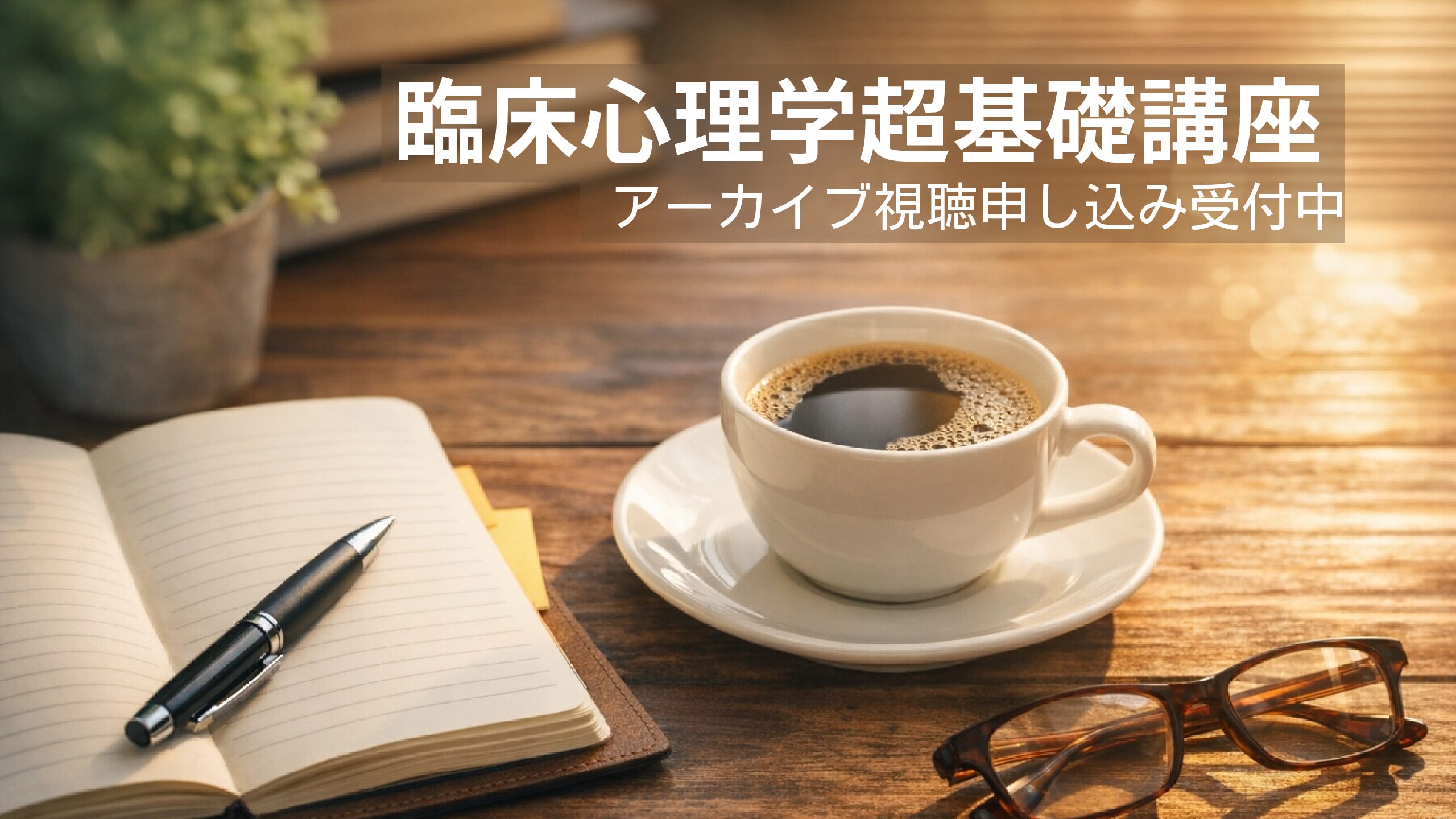【人に学ぶ】剛を内に秘め、柔を生かす──晏子という人のかたち

「剛を前に出せば敵をつくり、柔に溺れれば信を失う」
この言葉は、臨床や支援の現場だけでなく、日々の人間関係や政治・教育の世界においても、私たちの立ち居振る舞いに深く関わる示唆を与えてくれます。
そのことを、2000年以上前に体現していた人物がいます。
春秋時代の斉(せい)の宰相、**晏子(あんし)**です。
小柄な宰相の、大きな胆力
晏子は三代の君主に仕えた、歴史的にも高名な宰相です。
彼はとても小柄だったと伝えられており、その体格を揶揄されることも少なくなかったようです。
しかし、その中に秘められた胆力と理知は、どれほどの大国の王であろうと、揺るがすことはできませんでした。
その象徴となる逸話が、楚の王とのやりとりにあります。
目次
Toggle【逸話1】楚王の侮辱と、晏子の返し
あるとき晏子は、斉の国の使者として楚を訪れました。
楚王はわざと粗末な車を用意し、「囚人の門」から晏子を通らせるという、明らかな侮辱でもてなします。
楚王は笑ってこう尋ねました。
「斉には人材がいないのか? どうしてそんなに背の低い者を使者にしたのだ?」
すると晏子は、表情ひとつ変えずにこう答えます。
「斉には背の高い者も賢者も大勢おります。
しかし、礼をわきまえた国に使者を送るときには、礼を尽くせる者を選ぶのがならわしです。
それでこの私が参りました。」
楚王は言葉を失ったといいます。
相手の侮辱に怒ることなく、かといって黙って耐えるわけでもない。
柔らかく返しながらも、その言葉の奥に鋭さと芯が通っている。
ここに、**「剛を内に秘め、柔をもって応じる」**という晏子の姿勢が如実に表れています。
【逸話2】荘公への静かな諫め
晏子はまた、斉の君主・荘公(そうこう)にも仕えていました。
しかしこの荘公、あまり政に熱心ではなく、宴席にふけることが多かったと伝えられています。
あるとき、荘公が三日三晩、酒宴ばかりで政務を顧みない日が続きました。
晏子はその間、病と称して出仕せず、四日目にようやく現れます。
荘公が「なぜ三日も来なかったのか」と問うと、晏子はこう言いました。
「私は、陛下がご病気かと思い案じておりました。
朝から晩までお酒にふけり、政務を行わぬご様子……
もし肉体の病でなければ、心の病ではないかと。」
ここでも晏子は、声を荒げることなく、穏やかな言葉に真意を込め、
君主に静かに鏡を差し出すようにして、自省をうながしました。
【逸話3】剋泣・三踊──別れに示した本心
晏子の忠誠と敬意が真にあらわれたのは、荘公が亡くなったときでした。
儀礼の場で晏子は――
**剋泣(こくきゅう)し、三たび舞いを捧げた(三踊)**といいます。
「剋泣」とは、感情を抑えきれずに泣き出すこと。
「三踊」は、深い哀悼と敬意をこめて三たび舞うこと。
晏子は、日頃から荘公の政治姿勢に諫言を重ねていました。
決して甘い顔ばかりしていたわけではありません。
けれど、そのふるまいのすべてに一貫していたのは、誠実な忠義と深い人間的なつながりだったのです。
剛を持って対した君主の死に、柔をもって涙をこぼす。
そこには、表裏一体となった真実のふるまいがありました。
剛を前に出せば敵をつくり、柔に溺れれば信を失う
晏子の生き方は、今の私たちにも問いかけてきます。
現代の支援、教育、対人援助のあらゆる場面でも、こうしたバランス感覚は欠かせません。
「強さ」だけでは、相手の心を閉ざしてしまう。
「柔らかさ」だけでは、信頼を築く軸が弱くなる。
だからこそ、
剛を内に秘め、柔が生きるような人間構造を成す
という晏子の姿勢は、今を生きる私たちにとっても、実に大切な学びなのだと思います。
揺らがぬ芯と、しなやかな関わり──臨床における「内剛外柔」という姿勢
臨床の現場において、私たちはしばしば、「どのように関わるべきか」という問いに立たされます。
目の前の人の話をどう聴くのか、どこに焦点を当てるのか、介入するか見守るか──
こうした判断の積み重ねは、一見些細に見えて、関係全体の質を大きく左右することがあります。
そのとき、何より大事になってくるのが、**支援者自身の「あり方」**です。
■ 「内剛外柔」とは何か
「内剛外柔(ないごうがいじゅう)」という言葉があります。
直訳すれば、内には剛(つよさ)を、外には柔(やわらかさ)を。
これは、たとえばこんな構え方を指しています。
-
内剛: 自分の中にぶれない判断軸、倫理観、人間観を持つこと
-
外柔: 相手や状況に応じて柔らかく、しなやかに関わること
つまり、芯はあるが、押しつけない。信念はあるが、固執しない。
このバランスが、支援の現場では非常に重要になってきます。
■ 揺れ動く現場でこそ、判断軸が問われる
臨床の現場というのは、「正解」があるようで、ない場所です。
Aさんにとって正しいことが、Bさんにはまったく響かないこともあります。
そこで私たちは、状況をよく見て、丁寧に聴き、文脈を読み、関係を築きながら、「この人にとって、いま、何が必要か?」を見極めていきます。
しかしそれは、単なる“柔軟さ”ではありません。
むしろ、どんな状況でもぶれない「内なる判断軸」があるからこそ、外には安心して柔らかく関われるのです。
■ 判断軸はどう育てられるか?
では、その「内なる判断軸」は、どうやって育っていくのでしょうか。
これは、一朝一夕で手に入るものではありません。
以下に、日々の実践の中で少しずつ育てていくための視点をいくつか挙げてみます。
◎ 1.大切にしている価値観を言語化する
自分は何を大事にしているのか?
たとえば、「人は変わる力を持っている」「関係性が安全であることが優先」など。
まずは、ぼんやりと信じていることを言葉にしてみるところから始めます。
◎ 2.ケースを振り返りながら「なぜそうしたか」を探る
面接のあと、「なぜ、あの質問をしたのか?」「なぜ、今は介入しなかったのか?」を振り返ってみる。
直感や流れに任せた判断も、あとから意味づけることで、自分の判断軸が明確になっていきます。
◎ 3.他者との対話で視点を増やす
判断軸は、自分の内側だけで育つものではありません。
SV(スーパービジョン)や振り返りの対話の中で、他者の考え方に触れ、自分の立ち位置を見つめ直すことも重要です。
◎ 4.揺れたときにこそ、芯を問い直す
支援者として迷ったとき、不安になったときこそ、「自分は何を大切にしたいのか?」を立ち返って問う機会です。
判断が定まらないとき、それは学びが深まる入り口でもあります。
■ 剛性をもった柔軟性こそ、実用的な支援の力になる
「剛を前に出せば敵をつくり、柔に溺れれば信を失う」──
これは、古代中国の宰相・晏子のふるまいをめぐって語られた言葉です。
彼は、剛をむき出しにせず、それを内に秘めることで、外の柔らかさが生きるような生き方を体現していました。
臨床の現場でも、同じことが言えるのではないかと思います。
剛を内に秘めることで、柔が本来の力を持つ。
そのような姿勢が、相手にとっても安心できる支援の土台になり、結果として「役に立つ関わり」に結びついていく。
この「内剛外柔」という構え方を、支援者自身の成熟のひとつの方向として、私たちも意識して育てていけたらと思います。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!