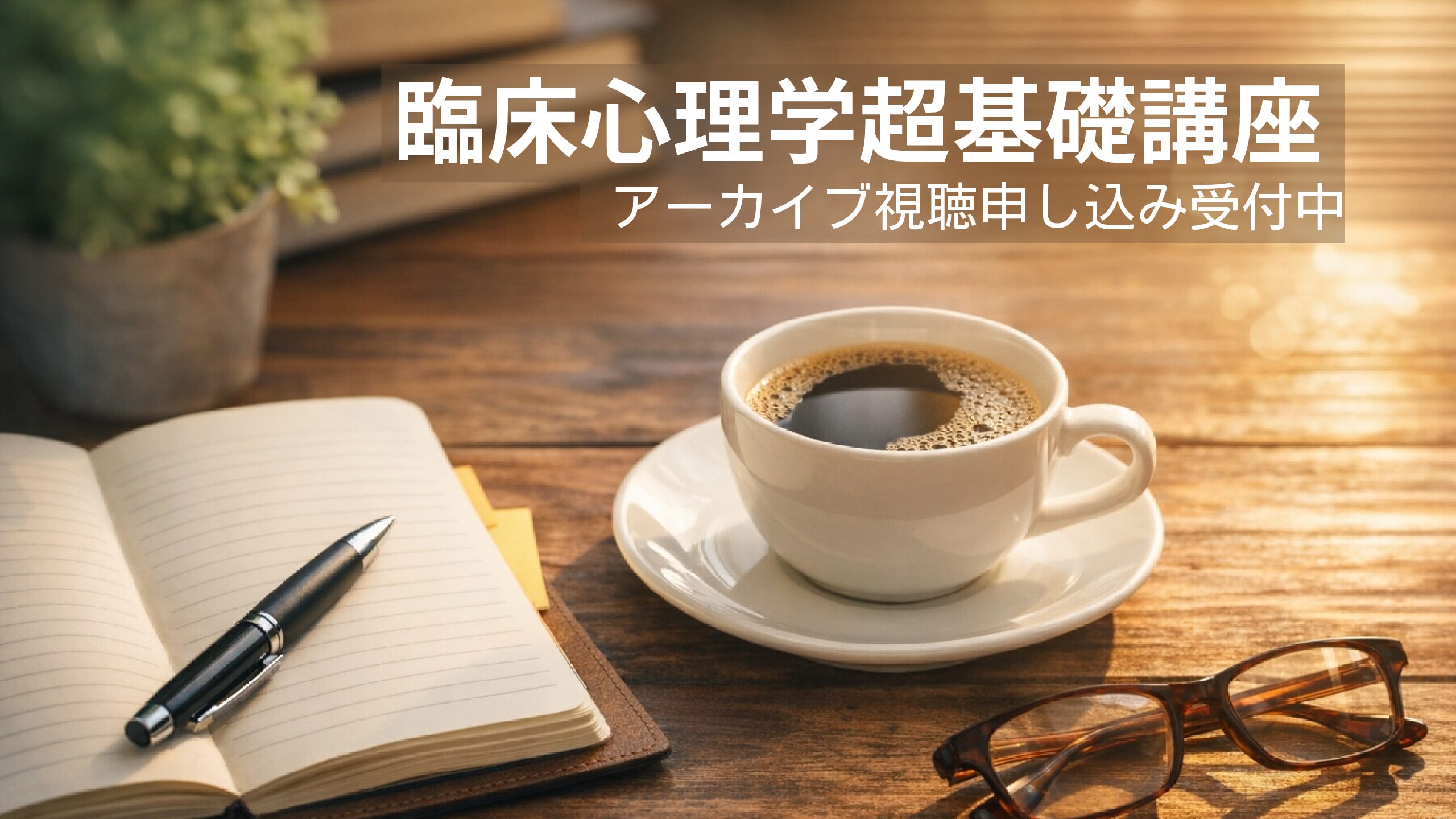個人臨床と組織臨床という、ちょっとややこしい話

今回は「個人臨床と組織臨床」というテーマを扱ってみようと思います。
「臨床」と聞くと、多くの方が思い浮かべるのは「カウンセリング室での1対1のやりとり」だと思います。あの、静かな部屋で向かい合って、相手の話を聴く――そんなイメージですね。実際、僕もその風景が大好きですし、そこにこそ臨床の本質があると思っています。
でも、スクールカウンセラーという立場で学校に関わっていると、ちょっと事情が変わってくる。
個人とのやりとりだけでは済まない、というか、むしろそれが“全体の一部”に過ぎなくなるような状況が日常的に起こるんです。
たとえば――
個別の生徒との面接、保護者との面談、教員との情報共有、ケース会議、学年会議、いじめ対策委員会、校内研修の依頼……。
そのどれもが「対人援助」なんですが、そのスケールがだんだん“個人”を超えて“組織”を対象にしていく。つまり、「組織臨床」という領域に足を踏み入れることになるんです。
目次
Toggleカウンセリングは「三層構造」
臨床心理の実践って、一言でいうと、だいたい三層で成り立っているように思います。
心地よいやりとりの層(関係性の構築) 情報処理の層(話を整理し、状況を理解していく) 計画的な介入の層(何をどう変えていくかを考える)
この三つが、ぐるぐる回っている。
でも、学校でのカウンセリングは、そこに「組織」が加わります。つまり、一人の生徒に関わっていても、それは同時に“学校全体に影響を与える”行為だったりする。
言い換えると、
個人への介入 ≒ 組織への介入
組織への介入 ≒ 個人への介入
という視点が求められてくる。
たとえば、不登校の子どもをどう支援するか――これはもちろんその子自身の問題なんですが、実はその背後に「担任の困り感」「学年運営の方針」「校長先生のスタンス」なんかが影響していて、そのすべてを視野に入れて動かないと、効果的な支援にはならないんですよね。
それでも、私たちは「個人臨床」から来た
ただ、僕たち臨床家は基本的に「個人主義」なんです。選んだ仕事からしてそうですし、少なくとも僕自身は、集団の中で押しつぶされそうになった人の声を拾いたくてこの仕事をしています。
表現できなかった思いや、抑え込まれてきた感情を、どうすれば安全に外に出せるか。そういう「個の回復」にずっと向き合ってきた。
だからこそ、学校という「集団の文化」の中で支援をしようとすると、いろんなことが起こるんです。
「浮く」問題、ありますよね
学校現場で、週1回だけ来る外部の人として関わっていると、「あーそういうこともありますね」くらいで流される程度で済むことが、常勤で職員室の一員として入り込むと、状況は一変します。
例えば子どもを少し甘やかすように見えるような関わり方、例えばまずケアが必要で、その後に成長を見込んでいても、それをきちんと説明せずに「今は見守りが必要」とか「とにかく今は甘えさせてあげて下さい」というような、単に子どもが困難を回避するのを助長するような提案をすれば。
「あの先生、なんか特別扱いしてるよね」
「それじゃこの子がますますわがままになるだけじゃない?」
みたいな声にならない反応が「浮き感」としてなんとなく伝わってくることもあるんじゃないでしょうか。
最初はうまくやっていたつもりでも、気がつけば周囲の雰囲気に居心地の悪さを感じたり、声をかけづらくなったりして、「あれ?これ、機能不全じゃないか?」と感じるようになってしまうこともありますよね。
迎合か、孤立か、それとも…
そうなると、二つの道が見えてきます。
迎合して「御用聞き」になる。
「なんでも教員の依頼には従いますよ」というスタイル。
もしくは、あまり教員集団には関わらず、個人臨床だけを淡々とやる。
どちらも、長くやっていくには難しい選択ですし、そのスタイルでいることで本来のSCの援助の機能、未然防止やコーディネートまで含んだ機能はいつまで経っても果たせないことでしょう。
前者では、「教職員の“今見えているニーズ”」ばかりに応えて、学校の“本当の課題”には手を出せなくなってしまう。
後者では、「カウンセラーって何してる人なの?」という不信感を生み、いざというときに声がかからなくなる。
第三の道:「合わせて、ズラす」
ではどうすればいいか。
僕が最近よく意識しているのは、「合わせて、ズラす」という関わり方です。
これは、家族療法でいう「ジョイニング(joining)」や、ミルトン・エリクソンの「ユーティライゼーション(活用)」の考え方に近いです。
まずは学校の文化、ルール、言語、文脈に“合わせて”入る。
以下の記事に詳しく書いてありますが。
【スクールカウンセリング】なんでスクールカウンセラーが学校でうまくいかないのか? 心のケアと課題解決能力の育成
「心のケア」だけでなく「課題解決能力の育成」を目標に入れ込むことで、学校の方針や教職員の文化に合わせた課題設定や介入方略を選択することが可能になります。
そして、信頼関係や理解が少しずつ深まってきたら、「ズラす」。今の関わり方に少しだけ別の見方や方法を加えてみる。
この、「合わせながらズラす」関わり方ができると、浮かずに介入できる、介入しながら居場所を失わない、という微妙なバランスが保てるようになる気がします。
組織臨床は“混沌”の中にある
ここまで来ると、個人臨床なのか組織臨床なのか、境目はあやふやになってきます。
ある子への支援が、担任の信頼感を高めることに繋がり、学校全体の不登校対応の指針が変わっていく――
ある教員へのリフレクションが、その人の学年運営や保護者対応のスタンスに影響して、子どもの居場所が増えていく――
そんなふうに、部分が全体に波及し、全体がまた個に戻ってくる。
部分は全体であり、全体は部分である。
でも、そんな混沌の中を泳ぎながら、「誰の声が今、埋もれかけているのか?」に目を凝らし、「そこにどうやって関われるか?」を日々考える。
これこそが、僕ら臨床家が「学校」という現場でできる、最も誠実な実践なんじゃないかなと思っています。
最後に:問いを持ち続けるために
スクールカウンセラーとして大事なことは、「正しい支援をすること」だけではなく、「問いを持ち続けること」だと思います。
この学校にとっての“本当の困りごと”はどこにあるのか? 今、見えていないけれど“変わっていける”部分はどこなのか? その子の沈黙の中にある願いは、どんな言葉で形になるのか?
答えが見つかることもあれば、見つからないまま関わり続けることもあります。
でも、その「問い」を持ち続けられることが、組織臨床というフィールドで、静かに、でも力強く介入していく鍵になるのではないかと思っています。
以下臨床心理学超基礎講座のお知らせ
傾聴からはじめよう:臨床心理学超基礎講座 (4/18開催)
臨床心理学超基礎講座 #1「傾聴からはじめよう」アンケート結果
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!