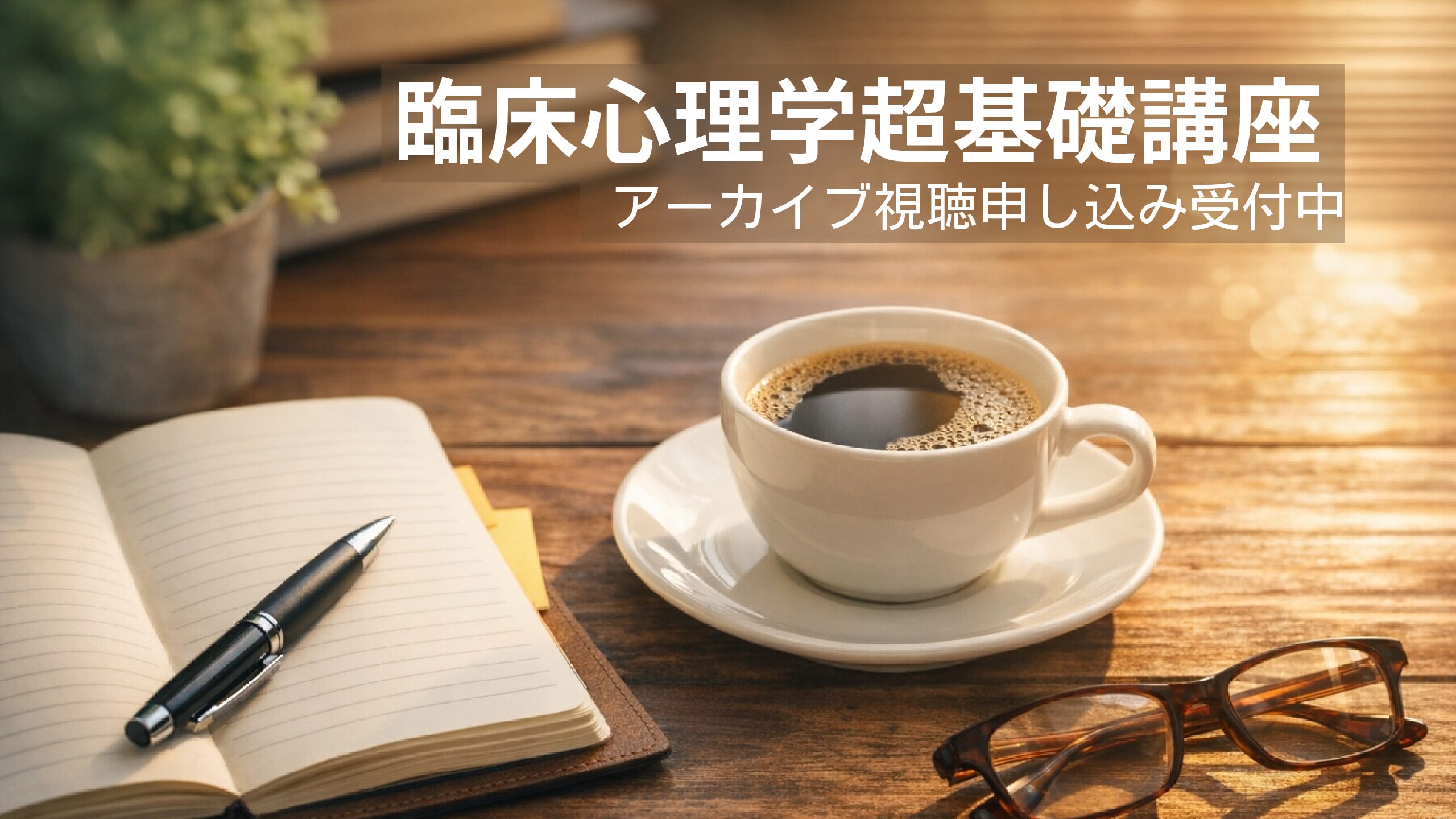心理臨床における協働の7原則 〜同じ地図を見ながら歩くということ〜

心理臨床やカウンセリングの現場で「協働」という言葉はよく耳にします。
でも、いざやってみると意外に難しく、「仲良くやること」と混同されることも少なくありません。
本来の協働とは、支援者と相手が同じ目的地を共有し、その道のりを調整しながら進むプロセスです。
ここでは、私がこれまでの臨床や学校現場で培ってきた「協働の7原則」をご紹介します。
これらは不登校支援や教員との連携、保護者面談など、幅広い場面で活かせる考え方です。
目次
目次
Toggle1.目的を共有する
協働は、単に一緒に作業することではなく、同じ方向を目指すことです。
例えば学校現場で担任の先生と動くとき、「不登校を減らす」とか「授業中の集中力を上げる」といったゴールが漠然としていると、お互いの動きはすぐにズレます。
以前、ある学校で担任の先生と一緒に子どもへの支援を考えたとき、私は「安心できる教室づくり」を目指していましたが、先生は「テストで平均点を取らせること」が目標でした。
このままでは協働はすれ違うだけ。
そこで、まず「この子が安心して授業に座れること」を共通ゴールに置き直しました。
同じ地図を見られたことで、支援の方向性もスムーズに揃いました。
2.小さな提案から始める
協働の入口は、相手が受け取りやすいサイズから。
いきなり「支援計画を大幅に変えましょう」と提案すると、相手は構えてしまいます。
ある保護者との面談で、「毎朝30分の家庭学習を」と提案したとき、表情が固まったことがありました。
そこで「今週は、登校前に5分だけ、好きな本を一緒に読む」という小さな提案に変えました。
これならできそうだと実践してもらい、その積み重ねが結果的に大きな変化を生みました。
3.相手の視点と専門的見立てを両立する
協働は、「相手に合わせるだけ」でも、「専門家の判断を押し付けるだけ」でも続きません。
保護者や先生が感じていることを丁寧に聴き取りつつ、こちらの見立ての根拠も明確に持っておくことが大切です。
たとえば「教室に入れない子ども」に対して、保護者は「甘えさせすぎでは?」と考えている場合があります。
そのとき私は、甘やかしではなく、回復のための段階的アプローチが必要だと説明します。
この「両方の視点を橋渡しする」ことが協働の核になります。
4.見通しを共有する
行動に入る前に、なぜそれをするのか、どんな変化を期待するのかを関係者全員で共有します。
たとえば「中休みに子どもと会う」こと一つでも、
-
担任からすると「落ち着かせるため」
-
私からすると「関係性を温めて授業参加につなげるため」
と、意図が違えば評価も違ってきます。
事前に見通しをそろえておくことで、同じ出来事を同じ意味で捉えることができ、次の手が打ちやすくなります。
5.力の流れを活かす
合気道の稽古で学んだことのひとつに、「力をぶつけない」という原則があります。
相手の動きやエネルギーの向きを変えたり、利用したりするほうが、結果的に前に進みやすい。
カウンセリングでも同じで、現場の流れやその人がすでに持っている力を使う方がうまくいきます。
これを**ユーティライゼーション(利用志向)**といいます。
ゼロから作るより、そこにある力を活かすほうが、協働はずっと自然に進みます。
6.現場に根付く形をつくる
支援者だけで完結するやり方は、短期的には成果が出ても長続きしません。
大事なのは、その場の人たちが自分ごととして続けられる形を作ることです。
以前、私が学校で導入した朝の声かけ習慣も、私が関与している間だけでは意味がありません。
担任や学年全体が自然に取り組むようになって初めて「文化」になります。
協働は、場を変えていく仕事でもあるのです。
7.不完全さを前提に計画する
協働の計画は、「予定通りにいかない」ことを前提に立てるべきです。
支援は生き物のように動き、クライエントや現場の状況も日々変わります。
計画段階で「必ずズレや想定外が起こる」と織り込んでおけば、そのズレを評価の材料にできます。
評価によって何がうまくいき、何が機能しなかったのかが明らかになり、そのフィードバックを次の介入に活かせます。
このサイクルを回すことで、見立てと介入の精度は少しずつ上がっていく。
不完全さは失敗ではなく、改善のための情報源なのです。
おわりに
協働とは、相手と横に並んで歩くことではありません。
同じ地図を見ながら、歩き方を調整し続けるプロセスです。
小さな一歩から始めて、見通しを共有し、相手の力を活かしながら、場に根付く形を作っていく。
その積み重ねが、心理臨床における協働の本質だと、私は思っています。
📢 心理臨床超基礎講座のご案内
この「協働の7原則」でお話しした内容は、私が開催している心理臨床超基礎講座のテーマとも深く関係しています。
現場で役立つ臨床心理の基本を、具体的事例とともに解説するオンライン講座です。
次回開催予定
第5回 心理臨床超基礎講座
テーマ:理解を伝える(助言とコンサルテーションについて)
日時:2025年8月15日(金)21:00〜23:00
形式:Zoomオンライン開催
※終了後には自由参加のアフターミーティングがあります。
参加者の方からは、
「ただの知識ではなく現場で使える」
「今までの自分の臨床を振り返って、自分が何をしようとしていたのか理解することができた」
「協働のポイントが腑に落ちた」
といった声をいただいています。
👉 詳細・お申し込みはこちら
心理臨床超基礎講座の詳細・お申し込みページ
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!