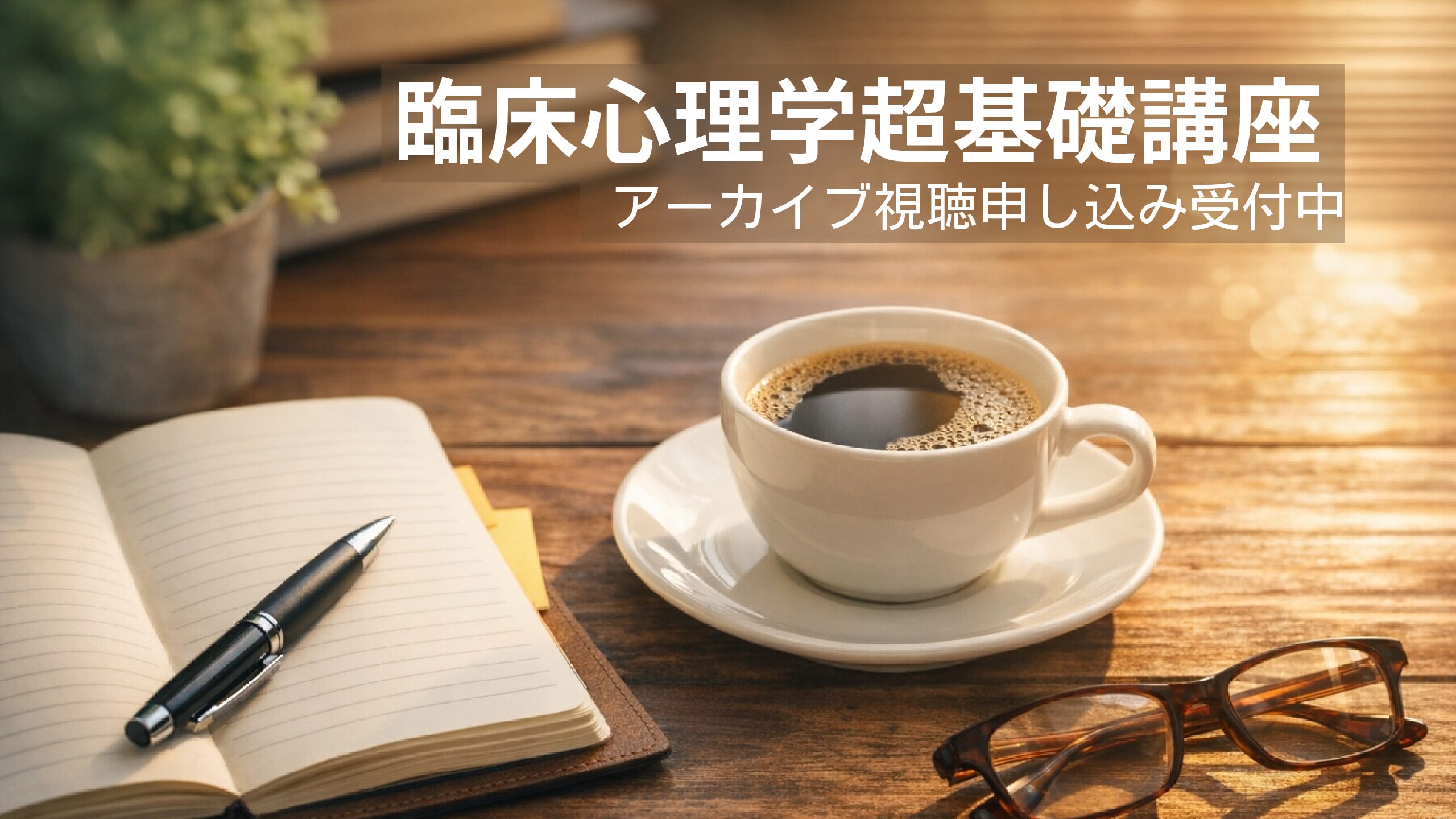カウンセリングにおける助言と共同作業:理解を伝えることから始める支援 臨床心理学超基礎講座#5のまとめ

先日開催された臨床心理学超基礎講座#5「理解を伝える〜助言とコンサルテーション」の内容について少しだけまとめて書かせていただきます。
目次
Toggle1. はじめに:安易な「助言」のリスクと「理解を伝える」重要性
カウンセリングプロセスにおいて、セラピストがクライアントを深く理解し、その内容を的確に伝えることで合意(コンセンサス)を形成することは極めて重要です。安易な「助言」は、本質的に「上から目線」になりがちで、クライアントの反発を招くリスクを伴います。これに対し、「理解を伝える」アプローチは、クライアントとの協同関係を築く上で大きな利点をもたらします。本稿では、この二つのアプローチを比較し、効果的な支援のあり方を探ります。
2. なぜ助言は失敗するのか?
助言がうまくいかない背景には、いくつかの典型的なメカニズムが存在します。
-
情報不足: セラピストはクライアントの状況を完全には把握しておらず、思いつきの助言は的外れになりがちです(例:「クレジットカードを使いすぎるなら、やめたらいい」)。
-
既知の失敗の提案: クライアントが既に試して失敗したことや、実行不可能なことを提案してしまい、信頼を損なうことがあります。
-
体験の軽視: 「こうした方がいい」という助言は、クライアントが現在進行形で体験していることの重要性を軽んじるメッセージになり得ます。
-
「正したい反射」: 人間には、間違った物事を訂正したくなる本能的な衝動があります。この反射が強いと、セラピストはクライアントの話の間違い探しに終始し、関係悪化やカウンセリング中断を招きやすくなります。これに対抗するには、曖昧な状態に耐える力「ネガティブ・ケイパビリティ」を養うことが求められます。

3. 効果的な支援の基本姿勢
3.1 「理解を伝える」ことの徹底
-
無知の姿勢(Not Knowing): 「あなたの専門家はあなた自身です。私は知らないので教えてください」という謙虚な立場を取ります。
-
コンセンサス形成: 「ここまでの私の理解で間違いないですか?」と常に問いかけ、確認を繰り返します。このプロセスを通じて、クライアントとセラピストの「共通理解」が蓄積され、それが後の介入における強固な土台となります。
3.2 「チェンジ」より「ノーチェンジ」の優先
助言は「今のままではダメだ、変わりなさい」という強力な「チェンジ」のメッセージであり、現状否定につながりかねません。まずは「ノーチェンジ」(ありのままを認める)を徹底し、クライアントの現状を肯定的に受け止めることで、信頼関係を十分に構築することが先決です。
3.3 セラピスト自身の内省
セラピストは、クライアントとの価値観のズレや、「助けなければ」という義務感から「力んで」しまうことがあります。このような違和感や身体反応(力み、汗)を自己観察し、性急に解消しようとせず、クライアントをより深く理解するための材料として保留・活用する姿勢が重要です。自身の理解が及ばないと感じたときは、「心の井戸」の底に当たったと捉え、「わからないので、もっと教えてください」とクライアントに教えを乞い、共に探求していくことが求められます。
4. 解決に向けた具体的なアプローチ
4.1 解決志向アプローチ:問題ではなく「解決像」に焦点を当てる
問題の原因追及ではなく、「どうなったら良いか」という未来の「解決像」に焦点を当てるアプローチです。特に生徒の成長を願う学校現場などと親和性が高いとされます。
-
未来志向の質問: 「学年末に、その子とどんな関係でいたいですか?」といった未来の理想像を尋ね、そこから逆算して「今できること」を考えます。
-
例外とリソースの発見: どんな困難な状況でも「うまくいっている部分(例外)」や、本人が持つ強みや関心(リソース)は存在するという前提に立ち、それを観察・発見し、活用します。
-
小さな介入と評価: いつものパターンに「異物(普段と違うこと)」を入れるような小さな課題を提案し、その後に起きた「少しマシになった」というレベルの小さな変化も肯定的に評価し、次のステップにつなげます。
4.2 課題の分解と具体化
大きな問題をそのまま扱おうとせず、具体的で実行可能な小さな課題に分解することが有効です。
-
抽象概念の具体化: 「元気」のような抽象的な言葉を、「カーテンを開ける」「水を飲む」といった具体的な行動レベルにまで分解し、その人にとっての「元気」の構造を理解します。
-
問題の細分化: 「不登校」という大きな問題を、「親との関係」「友人への不安」「勉強へのプレッシャー」といった構成要素に分解します。これにより、本人の世界観を深く理解できるだけでなく、関係者が協力して取り組める小さな課題に切り分けることが可能になります。
5. 「協働(コラボレーション)」という哲学と実践
5.1 協働関係の構築
-
クライアントは専門家: クライアント自身を「自分の問題における最高の専門家」とみなし、尊重します。保護者や教師もまた、それぞれ子育てや教育の専門家として捉え、相互に助言し合う関係を目指します。
-
問題の外在化: 「彼が問題だ」と個人に帰属させるのではなく、「彼が陥っているこの状況が問題だ」と捉え直します。これにより、本人も問題を解決するチームの一員として迎え入れることができます。
-
自分の課題として捉え直す: 「クライアントが変わらない」と嘆くのではなく、「クライアントの変化を助けられない私」という自身の課題として捉え直すことで、無力感から脱し、主体的に関われるようになります。
5.2 チームとしての支援
コンサルテーションの場では、まず相談者(教師や保護者)のこれまでの努力や苦労を十分に聞き、ねぎらう(エンパワーメントする)ことが最優先です。子どもの味方になる前に、まず目の前の相談者の味方になることで、支援の連鎖が生まれます。学年全体の教師が一致団結するなど、チームとして関わることが大きな力となります。
6. 事例に学ぶ介入の技術
-
不登校気味の生徒: 毎朝校門で腹痛を訴える生徒に対し、「行きたくない気持ちと戦いながらも、門まで来たこと自体が素晴らしい」という見方を提示。「よく来たね」と本人が既に達成している成功を認める声かけを提案し、状況が改善しました。
- 授業中に寝る生徒: 悪循環の仮説を立て、指導一辺倒ではなく、生徒の「寂しさ」や「居場所のなさ」に焦点を当てました。授業にクイズを取り入れたり、甘え行動を受け止めたりすることで、学校が安心できる居場所となり、生徒は本来の姿を取り戻しました。
7. 結論:効果的な助言は強固な協働関係から生まれる
公認心理師の業務には「助言」が含まれますが、効果的な助言は、その場しのぎの思いつきであってはなりません。それは、傾聴を通じてクライアントの生活(心理・社会・生物的側面)を深く理解し、見立てを立て、問いかけと確認を通じて「共通理解」を形成するという、強固な土台の上に初めて成り立つものです。支援とは、専門家が一方的に答えを与える行為ではなく、クライアントを専門家として尊重し、共に解決策を探求していく「協働作業(コラボレーション)」そのものであると言えるでしょう。
次回開催予定
第6回 心理臨床超基礎講座
テーマ:まとめと質疑応答
日時:2025年9月19日(金)21:00〜23:00
形式:Zoomオンライン開催
※終了後には自由参加のアフターミーティングがあります。
参加者の方からは、
「ただの知識ではなく現場で使える」
「今までの自分の臨床を振り返って、自分が何をしようとしていたのか理解することができた」
「協働のポイントが腑に落ちた」
といった声をいただいています。
👉 詳細・お申し込みはこちら
これまでの講座の内容も全て録画視聴(約1年間の予定)が可能です。
-
第1回(4月18日):傾聴からはじめよう
→ 傾聴は知っているだけではなく、「できる」こととの間に大きな距離があります。解像度を一緒に上げていきましょう。 -
第2回(5月16日):治療構造と転移
→ “治療の枠”をどう考えるかについて深掘りします。 -
第3回(6月20日):見立て
→ 「そんな見立てもアリなの?」という実践的な方法をお伝えします。 -
第4回(7月18日):共感
→ 共感は奥が深くて、踏み込んでいくととても面白いテーマです。 -
第5回(8月15日・お盆):理解を伝える(助言とコンサルテーション)
→ 言い方ひとつでクライアントの反応が大きく変わります。ここでは“抵抗処理”の技法にも触れられたらと思っています。 -
第6回(9月19日):まとめと質疑応答
→ 全体の振り返りと、皆さんの疑問にじっくりお答えします。
いずれの講座も、参加者の皆さんや、参加されない方の声も取り入れながら、今まさに作っているところです。「こういうところに困っている」といった声に応じて、内容を調整していきたいと考えています。
▼ 詳細・お申し込みはこちらから: https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854

オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!