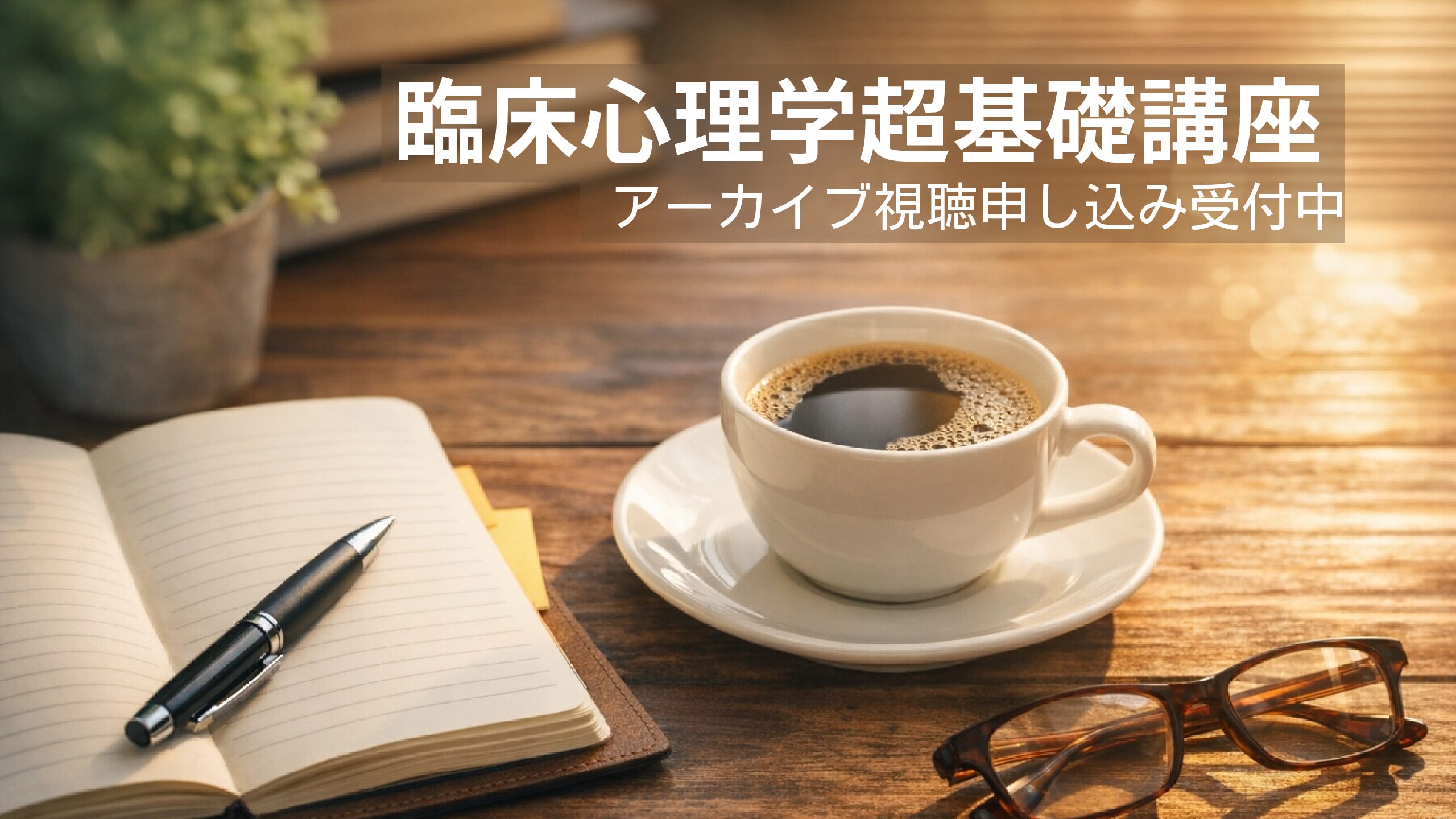不登校とゲームの関係をどう捉えるか 〜関わり方の質に注目する〜

はじめに
不登校の子どもが長時間ゲームに没頭している姿を前に、保護者が不安を募らせるのは自然な反応です。
「このままで将来大丈夫なのか」「依存にならないか」という懸念は、多くの家庭で共通しています。
本稿では、ゲーム行動をどのように理解し、支援的に関わるかについて整理します。
「承認」のあり方:受動と主体の違い
子どもがゲームを望んだときに、しぶしぶ許可を出すのは「受動的承認」にあたります。これは表面的な受け入れに留まり、保護者自身にフラストレーションを残すことも少なくありません。
一方「主体的承認」とは、子どもの選択に価値を認め、積極的に意味づける関わりです。
「学校に行っていなくても、自分の時間を楽しむことは大切だよね」
と声をかけることで、保護者と子ども双方が安心できる関係性を築きやすくなります。
ゲーム時間の調整:現実的な再設定
無制限にゲームを許可すると生活リズムが崩れやすい一方で、厳格な禁止は関係性の悪化を招きます。
実践的には、既存のルールを現状に合わせて緩和・再設定することが有効です。
例:
- 「1日2時間」などの時間制限
- 「午前中は自由にOK」などの時間帯指定
- 「登校時間帯は控える」などの現実的ルール
重要なのは、子どもと合意形成を図りつつ、合わなければ柔軟に見直すことです。
「せっかく」と「ただでさえ」の視点
不登校期の過ごし方は、大人の framing(枠づけ)に左右されます。
- 「せっかく学校に行っていないのだから」:新しい体験や活動を探す機会と捉える。
- 「ただでさえ学校に行っていないのだから」:不足や欠落を補填しようと焦る視点。
前者は可能性を広げ、後者は子どもの自己評価を下げやすい傾向にあります。
ゲームの心理的機能
支援の現場で理解しておきたいのは、ゲームが単なる娯楽にとどまらず、
- 安心感の獲得
- 自己コントロールの実感
- 外界との一時的遮断による回復
といった心理的役割を果たしている場合があるという点です。
保護者が「現実逃避」とみなす行動も、実際には自己調整の手段になっている可能性があります。
支援者への示唆
ゲームをめぐる支援で大切なのは、
- 「ゲームを許す・禁止する」という二分法を超えて、関わり方の質に焦点を当てること。
- 子どもが「自分の時間を自分で選べる」と感じられるような環境づくりを意識すること。
- 保護者の不安や葛藤を受け止めつつ、「主体的承認」へとシフトできるよう伴走すること。
声かけの中に「あなたには価値がある」
というメッセージが日常に織り込まれていくことが、次の一歩を支える力になります。
おわりに
不登校とゲームの関係を考える際、問題は「時間の多寡」ではなく、その関わりが子どもの成長にどう寄与しているかです。
支援者は「安心」「主体性」「関係性」の3つの観点から、保護者と共に調整を重ねていく必要があるでしょう。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!