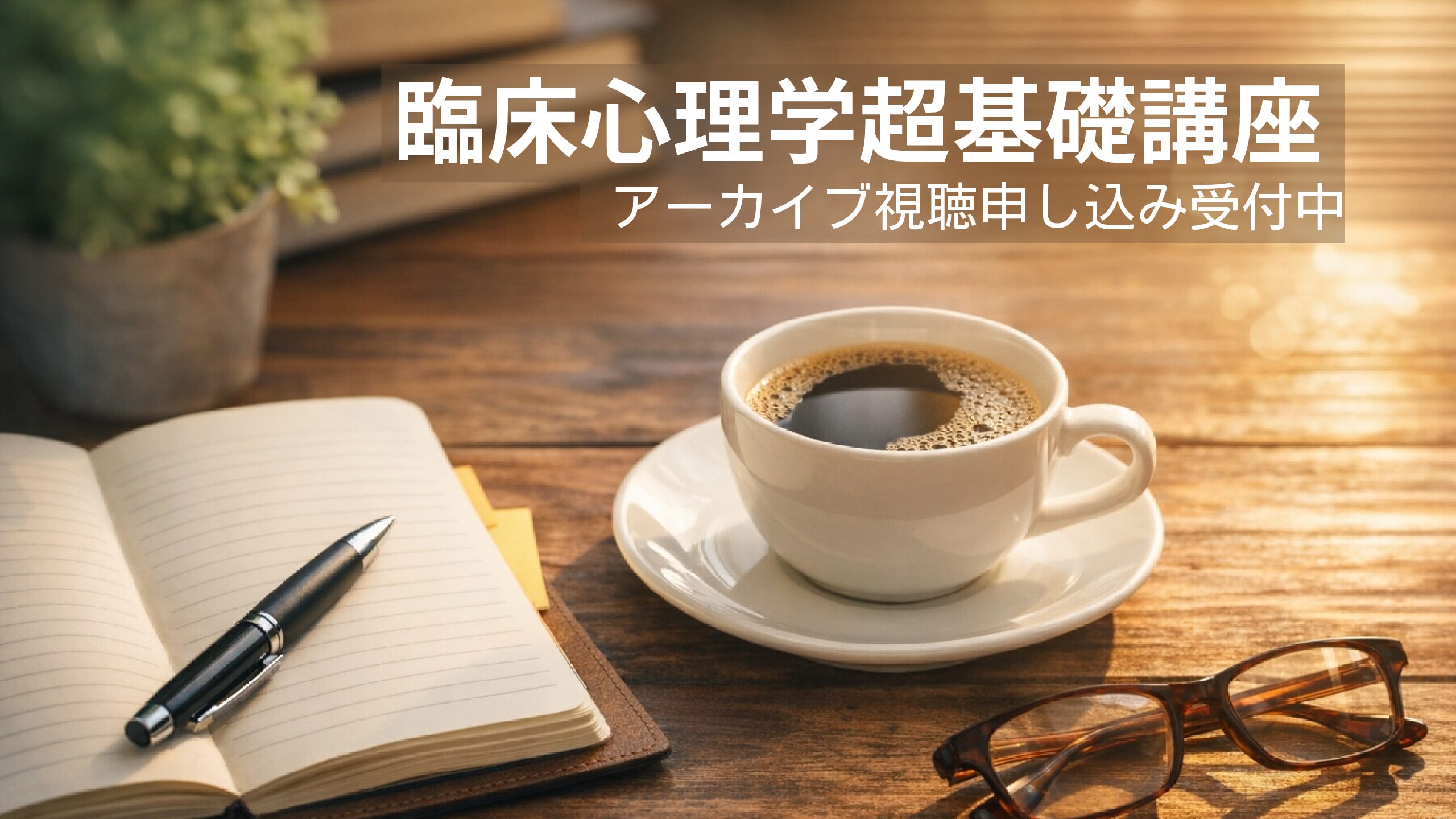カウンセリングにおける“文脈を聴く”ということと”不思議がる”こと

カウンセリングにおける“文脈を聴く”ということ
「想像力」と聞くと、どこか物語を創るようなイメージがあるかもしれません。けれど、心理臨床の現場で求められる想像力とは、もう少し地に足のついた、実践的な力のことを指します。
それはつまり、「仮説を立てる力」、あるいは「見立てを生成する力」と言ってもいいかもしれません。
たとえば、目の前のクライアントが今、どんな話をしているのか。その“話の内容”だけでなく、「なぜこのタイミングで、この話をするのか」という“話す文脈”に目を向ける。こうした視点が、臨床家には欠かせません。
目次
Toggle不思議がることから始まる臨床
精神分析家・成田善弘先生は、臨床において大切なのは「不思議がること」だと語っています。
精神分析家・成田善弘先生は、臨床の出発点として「不思議がる」ことの大切さを繰り返し説いています。
「不思議がる」とは、クライアントの語る内容や沈黙に対して、即断や先入観をもたずに、純粋な好奇心で向き合う姿勢のこと。たとえば、普通なら聞き流してしまいそうな言葉にも、「なぜこの人は、今このタイミングでこの話をしているのだろう?」と、立ち止まって考えること。それは、表面的な理解を超えて、関係の文脈を読み取ろうとする治療者の態度です。
この「不思議がる」姿勢は、患者自身が自分の内面に気づき直すきっかけとなり、自己洞察を深めていく手がかりにもなります。そしてそれは、単に観察するというよりも、クライアントとの関係の中で生まれてくる「今、ここ」に立ち会う在り方でもあります
「なんで今この人、この話をしてるんだろう?」
「なんでこのタイミングで、私にこの話をするんだろう?」
ただ話を“聞く”だけではなく、その奥にある「気持ちの流れ」や「関係の意味」に耳を澄ませる。これが、“文脈を聴く”ということなのです。
内容だけじゃない、「関係のなかでの言葉」
カウンセリングの場では、言葉は「内容」としてだけでなく、「関係のなかでの表現」として発せられます。
たとえば、クライアントが不登校の子どもについて話している。表面的には「子どもの悩み」ですが、実際には「自分の育て方を責められているようでつらい」という気持ちが背後にあるかもしれません。
そんな時、僕はこう聞くことがあります。
「ひょっとして、話すのちょっと気が重かったりしませんか?」
「ご自身の意志というより、先生に勧められて来られた感じでしょうか?」
そう問いかけると、「実は、、、」と、本来の相談ごとの手前にある、今ここにいる経緯や、その人にとってのこの相談の意味について語ってもらえることがあります。
そうして相談に至る前提を共有することで、相談の足場がカチッと固まるのではないかと思います。
“話したくない”という感情に気づく
「話したくない」「まだ準備ができていない」というクライアントの感情を、僕らが想像できるかどうか。ここに臨床の入口の大切な分かれ目があります。
誰かに促されて無理にカウンセリングに来た人に、「じゃあ始めましょう」と淡々とセッションを始めてしまえば、クライアントの心は閉じたままです。
けれど、「今回は話したくない感じですか?無理に話さなくても大丈夫ですよ」と言えること。ときには「今回はここまでにしておきましょうか」と提案できること。それが、その後の関係の土台になることもあるのです。
言葉よりも先に動く、身体の“サイン”
もうひとつ、大切にしているのが「身体の動き」や「表情」です。
言葉はコントロールできても、身体の動きや表情はなかなかごまかせない。会話のテンポやうなずき、ちょっとした視線のズレ。それらが、今この人が本当に話したいのか、話せないでいるのかを教えてくれることがあります。
「学校、爆発しちゃえばいいのにね」——余白をつくること
不登校の子どもに、「じゃあ学校に行くためにこうしよう」と言うのは、あまりうまくいきません。
東北大学の若島孔文先生との対談で、不登校の子どもが親に学校へ連れられてきて、「本当は学校に行きたいんです」と話された時、若島先生はこんなふうに問い掛けたそうです。
「君、本当は“学校なんて爆発しちゃえばいい”って思ってるんじゃない?」
すると、「いやいや、そんなことないですよ」と言いつつ、少し笑って場が緩む。その結果、学校に行きたくない気持ちも、「実はちょっとあるかも」と言えるようになる。
これは、「本来は扱えなかったことを扱えた」ということかと思います。
そもそも学校なんて行きたくないけど、この状況では「行きたい」と言わざるを得ない、という状況に言わされている言葉かもしれない、という文脈に気づけるかどうか?ここが難しい。
そして「爆発しちゃえばいい」という言葉は「本当は学校になんて行きたくないのに、そうも言えないこの状況」をいとも簡単に吹き飛ばしてくれました。
つまり「学校に行きたくない」という気持ちも扱える場になったということです。
文脈を読み、対話の底を抜く。
それが、相談の幅を広げる鍵になります。
クライアントは、必ずしも“話したい”わけではない
ここで大切なのは、クライアントが「話したいことが明確にあって話しているわけではない」ことも多いという点です。
言葉があちこちに飛んでしまう人もいれば、自分の話したいことを自分で分かっていない人もいます。そんな時、「あなたは何が話したいんですか?」と聞くのではなく、話の流れに寄り添いながら「今の話、ここが中心でしたね」と一緒に整理していく。
それが、“伴走する”ということなのかもしれません。
最初の一言で、すべてが決まってしまうこともある
カウンセリングの最初の数分間で、相談の成否が決まることがあります。
言葉を尽くしても、相手が「ここでは話せない」と感じたら、その後の関係は閉じてしまう。
だからこそ、最初の声のトーン、言葉の選び方、そして「今、話したくないかもしれない」という想像力。
それらすべてが、相談という営みを支えているのだと思います。
「話したくない」ことを、話せる場所へ
僕たちはつい、相手が「話したい」から話していると思ってしまっていることがあります。
でも、本当に必要なのは、「話したくない」ことが「話してもいいかもしれない」と思える空気をつくること。
それは、まだ語られていない文脈を読み、想像し、対話の中に余白を作ることかと思います。
研修情報のご案内
2024年4月より、「臨床心理学と解決志向の超基礎講座」を開講します。
大学や大学院で学んだ「基礎」はとても大切なものですが、いざ実践に出ると「そのままではなかなかうまくいかない」と感じた経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この講座では、「基礎と現場をどう結びつけるか?」という視点から、あらためて基礎をブラッシュアップしていくことを目指します。
対象は、対人支援職の方だけでなく、支援職を目指す学生の方も歓迎しています。
初回4月18日のテーマは「傾聴」について。
今回のブログの内容は、基礎講座の内容に沿ったものです。
当日はさらに具体例を交えつつお話しさせていただきます。
▼ 詳細・お申し込みはこちらから: https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854

また、講座準備の一環として、「カウンセリングに関する基礎的な困りごと(傾聴・関係づくり・治療構造など)」に関する情報を集めています。
実際の現場で感じていること、疑問に思っていることを、以下のアンケートフォームからお寄せください。
皆さまのお声をもとに、より実践的で役に立つ講座にしていきたいと考えています。
▼ アンケートご協力のお願い: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RJ60vZgjrulKrvRrRF5VqnCZnZlFzgf6wBByqvrrBVj1gA/viewform?usp=sharing
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!