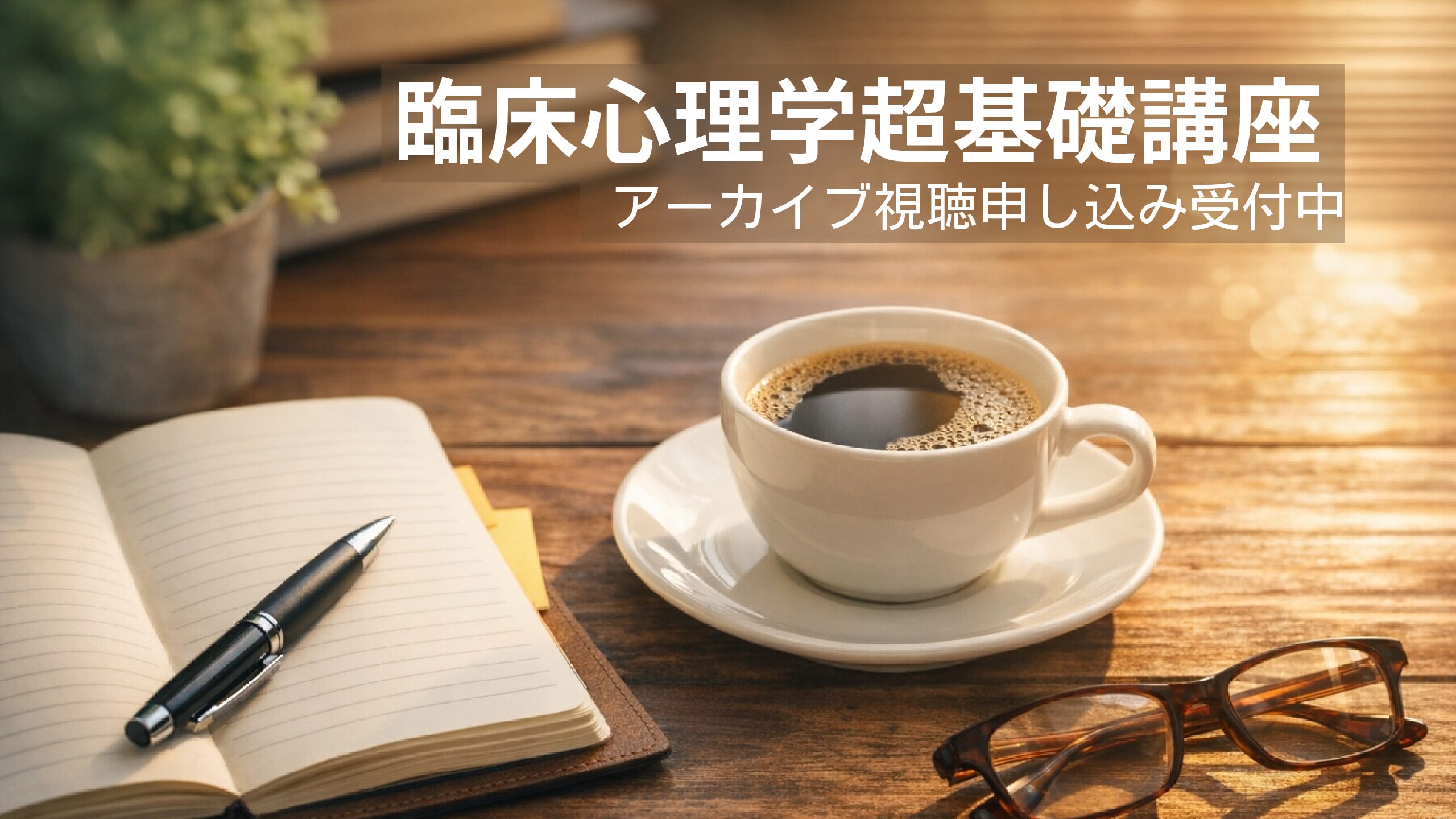学校との情報共有の仕方について➖願いから始まる協働 ➖

目次
Toggle― 教員との“濃淡”ある関わりと、願いから始まる協働 ―
スクールカウンセラーとして学校に入っていると、いつも悩まされるテーマがあります。
それは「先生方と、どこまで関わるべきか?」ということ。
SVでも先生方との関わりや情報共有の仕方について助言を求められることがあります。
最初の頃は、「全員に丁寧に、一生懸命関わらなきゃ」と思っていました。
でも、現場で過ごすうちに気づいたんです。
どの先生にも同じように関わろうとすることこそが、むしろ無理を生むということに。
関わりには“濃淡”があっていい
教員とスクールカウンセラーは、それぞれに立場があり、視点があります。
そして当然、先生方にも日々の忙しさや、関心の向き、不安や戸惑いがある。
だから私は、すべての先生に同じスタンスで関わろうとはしません。
関わりを“エネルギーを込めて濃くすべき場合”と、“相手の負担を少なく、関わりを控えめにする場合”とに分けて、こちらの出方を調整するようにしています。
たとえば、明らかにSCに期待をしていて、SCの関わっている子どもの様子を丁寧に教えてくださっている先生。
SCと連携した関わりに明らかに手応えを感じてくれている先生。
そういった先生とは、ご都合を聞きつつも、しっかり話す時間を取れるように関われるかもしれません。
一方で、子どもや保護者がSCと面接をしているのにも関わらず、SCに期待を持たず、あまり関心を持っていない場合もあります。
そういう場合は、担任の負担ができるだけ小さい関わりに止まる必要があります。
そのかわり、「最小限の報告」や「タイミングを見ての軽い声かけ」など、細く長く、関係をつなぐ工夫をしていきます。
最初は軽やかに。反応を見て、踏み込み方を決める
私がよくやるのは、時間を取らない軽めの報告や、簡単な付箋を使った伝言や情報共有くらいで留めておくようにします。
それに対して、先生が後日声をかけてくれたら、「今はもう少し話をしてもいいタイミングかもしれない」と判断する。
そんな時にちゃんと話せるように、見立てと方針について言葉にして準備をしておく必要があります。
これが繰り返されることで、期待がなかった場合でも、少しずつ期待や関心が上がっていくことがあります。
逆に、特に反応がない場合は、「今はまだ入らなくていいかな」と一旦距離を保ちます。
半年から1年くらいのスパンで、無理なく関係を温めていく意識でいく、という心構えがちょうど良いと感じています。
担任を「通す」ことの意味
保護者や子どもと関わるとき、私は原則として担任の先生を通すようにしています。
なぜなら、学校の中で子どもを責任を持って“預かっている”のは担任だからです。
「最初の一報だけは担任に通しておく」「担任の見通しとニーズについて把握する」「こちらの見立てと見通しはちゃんと伝える」。
これを丁寧にすることで、スクールカウンセラーとしても安心して動けますし、教員側の信頼も得やすくなります。
教員の“願い”を、成長の文脈で引き出す
スクールカウンセラーが学校内でうまく機能するためには、
「学校教育に関する理解」と「教員との信頼関係」だけでなく、
もう一つ、教員自身が子どもに対して持っている“願い”を、成長の文脈で丁寧に引き出すことが大きなポイントになります。
そのためには、こんな未来志向の問いかけがとても大切です。
「年度の終わりや卒業のとき、この子がどんなふうに育っていたらいいと思いますか?」
「先生とどんな関係でいられたら、先生ご自身は納得感を持てそうですか?」
先生自身もまだ言葉にしていない願いを、一緒に言語化し、形にしていくこと。
それが、支援の“方向性”を共有するための第一歩になります。
“小さな提案”から始まる協働
たとえば、子どもと中休みに面接をすることになっていたとして、
それが「なんとなく話しているだけ」の時間になってしまうことがあります。
でも、本来は──
「なぜこの子と会っているのか?」
「会うことでどんな意味を生み出したいのか?」
そういった見通しを持つことが、セラピストには求められます。
さらに重要なのは、その見通しを担任と共有しておくことです。
担任のニーズや願いと、スクールカウンセラーの見立てが重なるとき、
支援の方向性がぐっと定まり、協働がしやすくなります。
そしてもう一つ大切なのが、
子ども自身の気持ちや都合がそこに反映されているか?
言葉にできていなくても、「会いたそう」「嬉しそう」といった非言語的なサインが、そこにあるかどうか。
子ども・先生・スクールカウンセラー、三者の間に“納得”の空気があるかどうかがとても重要です。
たとえば、こんなケース。
「この子、授業中はすごく気を張ってがんばってる。4時間目になると電池切れみたいに崩れてしまう」
「家庭では家族も忙しく、十分に気持ちを受け止めてもらう場が少ないようだ」
そんな背景があるとき、
週に1回でも中休みにカウンセラーと会って話す時間が、その子の“楽しみ”や“癒し”になることがあります。
そしてそれが結果的に、「3〜4時間目の元気さ」につながってくることもあるかもしれません。
大切なのは、それをちゃんと“見通しを持った支援”として先生と共有すること。
そのうえで、たとえばこう声をかけます。
「今日の午後、○○さんの様子どうでしたか?少し元気出てた感じありました?」
このようなやり取りを通じて、先生と一緒に支援の“評価”をしていきます。
うまくいっていれば続ける。
子どもがイヤイヤになってきたり、逆に気を遣いすぎて疲れていそうなら、サポートの形を変える。
こういった**小さな“協働の手応え”**が、
先生の中に「カウンセリングって意味があるかもしれないな」という実感を育ててくれるんです。
願いに寄り添う支援こそが、意味のあるコンサルテーションにつながる
先生が願っていることに対して、
「それならこんな関わり方ができそうです」と提案をする。
このとき、「こちらの理屈で動いている」感じではなく、“先生の願いを叶えるために”というスタンスで提案すると、相手にも自然に届きやすいと感じます。
これは単なる報告ではなく、まさに協働の出発点=コンサルテーションになるんですよね。
おわりに:支援は“押す”ものではなく、“重なり”を探すもの
すべての先生と同じように関わる必要はありません。
むしろ、それぞれの“関心の持ち方”や“願いのあり方”に寄り添って、関わりの形を調整することこそ、スクールカウンセラーの専門性だと思っています。
そして、先生と「この子のために、こうなったらいいよね」と願いを共有できたとき、
それはもう立派な“協働”の始まりです。
臨床心理学超基礎講座のご案内
毎月第3金曜日の21時〜23時に開催予定です。
どの回もアーカイブ視聴が可能です。
-
第1回(4月18日):傾聴からはじめよう
→ 傾聴は知っているだけではなく、「できる」こととの間に大きな距離があります。解像度を一緒に上げていきましょう。 -
第2回(5月16日):治療構造と転移
→ “治療の枠”をどう考えるかについて深掘りしますが、治療外の文脈をどうやって構造の中に取り込むのか?みたいな話になってきています。精神分析の治療構造より、少し広い観点でお話しできたらと思います。 -
第3回(6月20日):見立てと理解
→ 「そんな見立てもアリなの?」と思ってもらえるような、面白い内容になると思います。 -
第4回(7月18日):共感
→ 共感は奥が深くて、踏み込んでいくととても面白いテーマです。 -
第5回(8月15日・お盆):理解を伝える(助言とコンサルテーションについて)
→ 言い方ひとつでクライアントの反応が大きく変わります。また今回のブログで書いた内容、コンサルテーションや情報共有の仕方や、“抵抗処理”の技法にも触れられたらと思っています。 -
第6回(9月19日):まとめと質疑応答
→ 全体の振り返りと、皆さんの疑問にじっくりお答えします。
そして、後半は10月17日から始まる『解決志向・超基礎講座』。どの理論的背景を持つ人にも役立つ内容を予定しています。
いずれの講座も、参加者の皆さんや、参加されない方の声も取り入れながら、今まさに作っているところです。「こういうところに困っている」といった声に応じて、内容を調整していきたいと考えています。
▼ 詳細・お申し込みはこちらから: https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854

また、講座準備の一環として、カウンセリングに関する基礎的な困りごとに関する情報を集めています。
実際の現場で感じていること、疑問に思っていることを、以下のアンケートフォームからお寄せください。
皆さまのお声をもとに、より実践的で役に立つ講座にしていきたいと考えています。
▼ アンケートご協力のお願い: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8RJ60vZgjrulKrvRrRF5VqnCZnZlFzgf6wBByqvrrBVj1gA/viewform?usp=sharing
それでは、またお会いできるのを楽しみにしています。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!