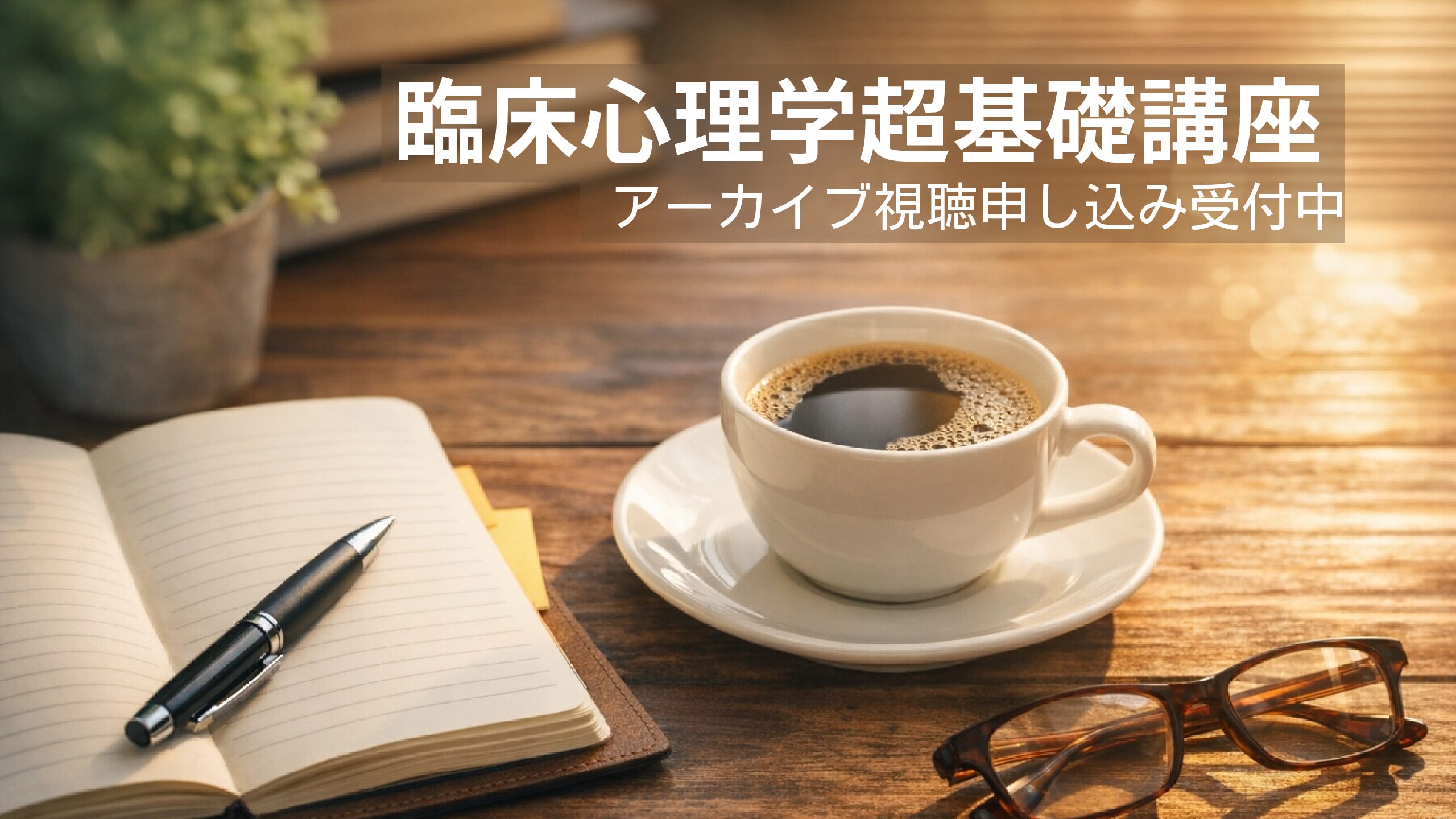困り感を持っていない(ように見える)人にどう関わるか?

目次
Toggle1. 困り感を持っていない(ように見える)理由には大きく2つのパターンがある
困り感を持っていないように見える人には、大きく分けて以下の2つのパターンがあると思います。- 実は困っているが、それを話したり明かしたりすることに抵抗がある
- 問題がない、つまり違う価値観や見方を持っているために、困り感を感じていない
2. 実は困っているが、話すことに抵抗がある場合
普通の発想では、「周りはこんなに大変なんだぞ。もっと困り感を持ってくれ」と、相手に周囲の困り事を思い知らせようとすることになりがちです。しかし、これは「困り感がない人=困った人」として見なしていることになり、その目線のまま関わると、よりつながりにくくなり、こちら側の要求も伝わりにくくなってしまいます。 そこで、臨床的な視点として考えられるのは、ズバリ「困り事や困り感の外側、関係ないところで関わる」ことです。問題に直接踏み込むのではなく、大回りしながらも、最終的にはそこにたどり着くという前提で付き合っていくことが大切です。これは家族療法やブリーフセラピーにおける「ジョイニング」や「ペーシングとリーディング」の考え方にも通じます。(側から見ると共感的理解に見えるかもですが) この場合、まずは相手の困りごとに対して無理に向き合わせようとするのではなく、関係を作ることが第一歩になります。その人が「困りごとに関わること」「向き合うこと」「実行すること」の難しさについて理解を深めていくことも重要です。
例えば、不登校の子供と関わるとき、登校について話すのではなく、その子が好きなことを一緒に楽しむことで関係を築いていくことがあります。家庭訪問に行き、その子がゲームをしていたら、ただ横で話を聞いたり、一緒にゲームの話をしたりするだけで、最初の一歩になることがあります。不登校の子供に毎回「学校の話」をしてしまうと、それは相手にとって苦痛な時間になってしまい、関係が遠ざかってしまうのです。
ただ、こうした関係づくりは単に「仲良くなる」ことが目的ではありません。時間をかけて関係を築くことで、相手が「話してもいいかな」と思えるようになり、結果的に困りごとに向き合うきっかけが生まれてくるのです。
(これ教師や支援者は、子供に対しては寄り添うことできるけど「大人」に対してはそうできないことが結構あります)
また、この過程では「本当は困っているけど話せない」という状況が見えてくることもあります。例えば、「学校に行かないことは問題ではない」と言いながらも、実は親自身が周囲の目を気にしていたり、「どうすればいいかわからない」と思いながらも、それを認めるのが怖かったりするケース、もしくはそもそも学校や教師を全く信用できていないケースです。こうした隠れた困り感を見つけていくには、「それを話せる関係」が前提となります。そのためにも、まずは関係を築き、「困っていることを話してもいい」と思える環境を整えていくことが重要なのです。
この場合、まずは相手の困りごとに対して無理に向き合わせようとするのではなく、関係を作ることが第一歩になります。その人が「困りごとに関わること」「向き合うこと」「実行すること」の難しさについて理解を深めていくことも重要です。
例えば、不登校の子供と関わるとき、登校について話すのではなく、その子が好きなことを一緒に楽しむことで関係を築いていくことがあります。家庭訪問に行き、その子がゲームをしていたら、ただ横で話を聞いたり、一緒にゲームの話をしたりするだけで、最初の一歩になることがあります。不登校の子供に毎回「学校の話」をしてしまうと、それは相手にとって苦痛な時間になってしまい、関係が遠ざかってしまうのです。
ただ、こうした関係づくりは単に「仲良くなる」ことが目的ではありません。時間をかけて関係を築くことで、相手が「話してもいいかな」と思えるようになり、結果的に困りごとに向き合うきっかけが生まれてくるのです。
(これ教師や支援者は、子供に対しては寄り添うことできるけど「大人」に対してはそうできないことが結構あります)
また、この過程では「本当は困っているけど話せない」という状況が見えてくることもあります。例えば、「学校に行かないことは問題ではない」と言いながらも、実は親自身が周囲の目を気にしていたり、「どうすればいいかわからない」と思いながらも、それを認めるのが怖かったりするケース、もしくはそもそも学校や教師を全く信用できていないケースです。こうした隠れた困り感を見つけていくには、「それを話せる関係」が前提となります。そのためにも、まずは関係を築き、「困っていることを話してもいい」と思える環境を整えていくことが重要なのです。
3. 違う価値観や見方を持っている場合
もう一つのパターンは、「問題がない」と考えているケースです。これは、単に困り感がないのではなく、「自分にとっては問題ではない」と思っている、または「違う価値観や見方を持っている」ということです。 この場合、相手を「困っていないから困らせなきゃ」と思うのではなく、「その価値観の中で何が大事なのか」を知ろうとすることが大切です。 例えば、不登校の子供を持つ親が「学校に行くことが全てではない」と考えている場合、支援者が「いや、でも学校には行くべきですよ」「後で困るのは子供です」などと伝えても、全く噛み合いません。ここで「もっと困ってほしい」と願うのではなく、「なんで学校いかなくて良いと思っているんだろう?」と関心を持って関わる、話を聞くことで、その視点の持ち方ににじり寄ることができます。 また「学校のことは置いておいて、大事に思っていることはなんだろう?」ということも関心を向けると良いかと思います。「子供が元気で楽しく過ごせることは大事」「学校ではないところで社会性を見につけててほしい」「何かの界隈でトップを取って欲しい」など色々あるんですよね。まずそんなところの話が聞けること、一緒に考えられることが、協力的な関係をに近づく一歩になるかと思います。4. 関係を変えるために:「ああ、なるほど、そりゃそう思いますよね」と本気で思うこと
どちらのケースにおいても、重要なのは支援者が「ああ、そりゃそう思いますよね」と本気で思えるとこまで理解が進むかどうかです。相手を「困っていないい人」と考えてしまうと、これはもう関係がうまく築けません。 例えば、「子供を無理に学校に行かせるつもりはない」と考えている親に対して否定的な態度を取るのではなく、「そう思うようになった背景には、いろいろなことがあったんじゃなかろうか?」と、その考えの背後にあるものについて関心を向けつつ関わることで、相手も「この人なら話せるかも」と思えるようになり、ることがあります。 そんな時に、そもそも専門家が「絶対に学校に行かせなければ!」とか「学校なんて行く価値がない」とか思っているとこれが難しいわけです。 「まあ究極、子供が自分の思いや決断を大事にできて、かつ幸せになっていけるなら、学校に行こうが行かまいがどっちでもいいんだけどね」くらいの緩めの気持ちでいた方が、支援はうまく回るなと思います。(この「どっちでもいいんだけどね」が本気で思えるかどうかってかなり大事だし、難しいことなのですがまた違う機会に書きます) 結局、支援者の姿勢そのものが、関係の質を左右します。「ギャップについて自分の価値で判断せずに、ギャップそのものについて肯定的な関心で関わる」ことが「一旦遠回りしても協働関係ができてくる」に繋がります。そこが支援のスタートラインなので、いきなりゴールを目指さずに、まずはスタートラインに立ちましょう、という話でした。研修のお知らせ
4月から、臨床心理学と解決志向についての超基礎講座を行います。大学や大学院で基礎を習うわけですが、その正しい基礎そのままでは、どうも上手くいかないと思いながら実践の中で、自分のやり方を見つけていくという実務家が多いのではないかと思います。基礎と現場をどう結びつけていくか?ということをテーマにもう一度基礎をブラッシュアップしていきませんか?という企画です。対人支援職の方のみならず、支援者を目指す学生の方も参加可能です。 https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!