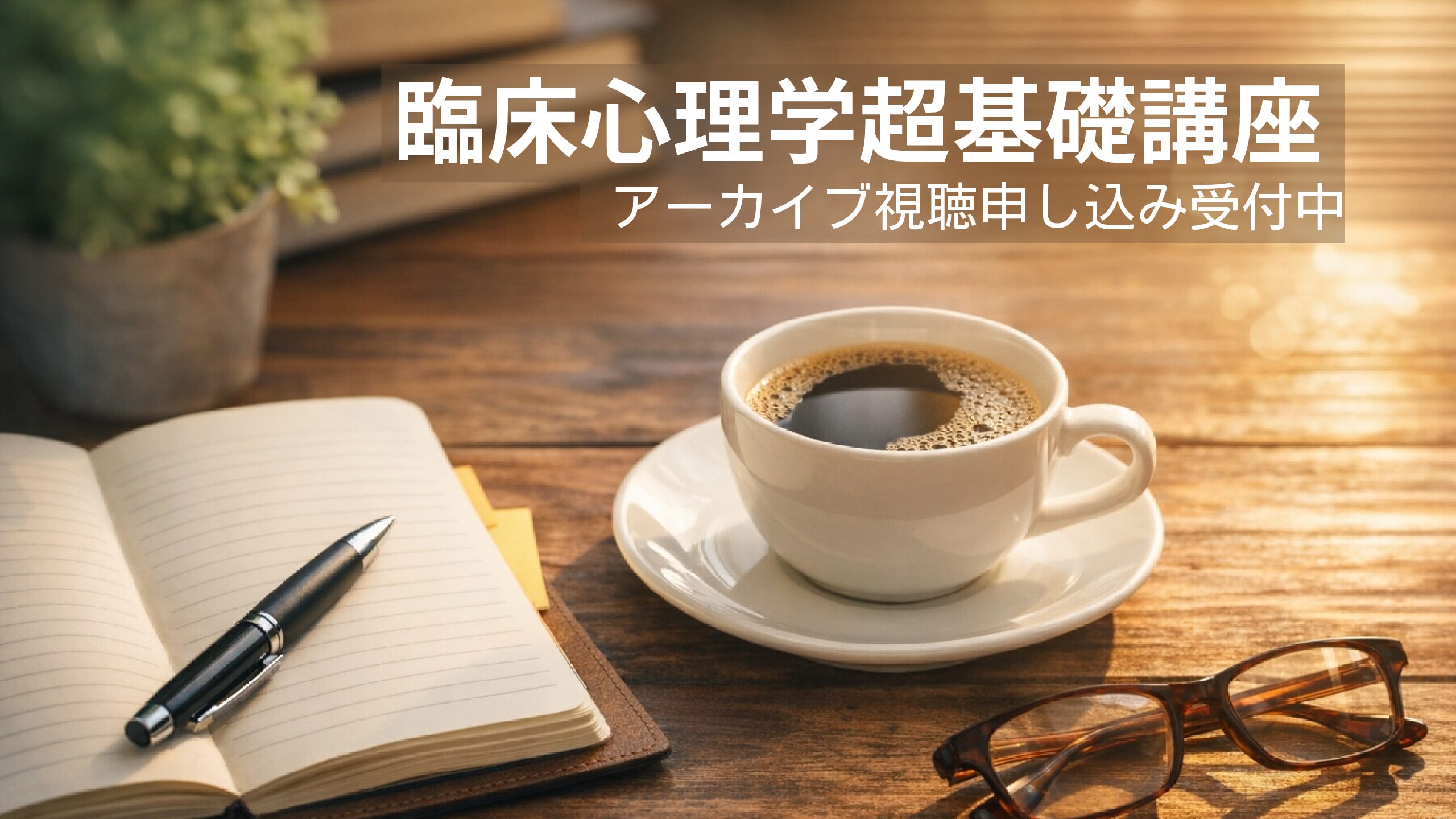子どもの「やりたい!」をどう受け止めるか?〜主体性を伸ばし経験の質と幅を担保する〜

子どもは成長の過程で、本当にいろいろなことに興味を示します。
「あれやりたい!」「これもやりたい!」と、目に映るものにどんどん手を伸ばしていきますよね。
もちろん中には、子どもの力ではまだ難しいこと、危険を伴うこと、バランスをとるのが難しいこともあります。
親としては「危ないからダメ」「あっち行ってなさい」と言いたくなる場面も多いのではないでしょうか。
今日は、そんな時にどう考えたらいいか、というお話です。
小さな「仕事」を任せてみる
2歳や3歳くらいになると、料理をしている親を見て「私もやりたい!」と言い出すことがあります。
ですが包丁も火もある台所は、正直なところ危険がいっぱい。手先の器用さもまだ十分ではないので、持ったものをこぼしたり、ケガをしてしまう可能性もあります。
そんな時におすすめなのは、やりたい仕事の中の一部だけを任せてみることです。
例えば――
ご飯に海苔を振りかけてもらう 子ども専用のフォークを食卓に運んでもらう 「ありがとう、いい仕事だったね」と伝える
こうした小さな役割を切り出して一緒にやることができると、子どもは「自分が料理に関わった」と感じられます。
そしてその関わりが家族に感謝される体験へとつながっていきます。
もちろん、調子に乗って「あれもやる!これもやる!」と言い出す子もいます。
でもそこで「今日はここまでね」と区切って大丈夫です。大切なのは、自分が関わって感謝された経験を残してあげることです。
安全に「参加できる部分」を探す
料理はハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。
そんな時は、もっと安全な日常の場面から始めてもいいでしょう。
洗濯物をたたむ・しまう テーブルの上にコップを置いてもらう お風呂掃除のときにシャワーをかけてもらう(多少びしょびしょになってもOK)
こうした関わり方なら、危険も少なく「やりたい気持ち」を満たすことができます。
子どもはいつまでも同じことをやりたいわけではなく、自分が満足したら別のことに注意が移ります。
ほんの「指先だけ」「つま先だけ」湯船につかるような関わり方が、意欲を損なわずに自尊感情を育て、体験の幅と質を広げるきっかけになります。
成長に合わせた関わり方
毎朝のように「卵をまぜまぜ」していると、最初はうまくできなかった動きが少しずつ上達していきます。
発達が進むにつれ、やっていることの解像度も上がり、「もっとこうしたい」「こうやってみたい」といった新しい工夫が出てくることもあります。
そんな変化に気づいたら、「前より上手になったね」と声をかけることも大切です。
一方で、突然「ガスの匂いがいや」「火が出て怖い」と理由をつけてやらなくなることもあります。
その場合は「じゃあ今日はお休みね」と、あっさり受け止めて構いません。
大切なのは、やりたいときに受け止めて、できる活動に落とし込むこと。
そして「やってもいいし、やめてもいい」という柔らかいマネジメントです。
親の余裕も大事
とはいえ、すべての「やりたい」を受け止めるのは現実的に難しいものです。
親だって忙しいし、余裕がないときも当然あります。
ですから無理に「全部やらせなきゃ」と思う必要はありません。
日常の中で「この部分なら大丈夫そうだな」と思える場面を見つけ、ほんの少し子どもの意欲に乗っかってみる。
その積み重ねが、子どもの意欲や自尊感情を育て、生活体験の幅を広げていくのではないでしょうか。
そしてここに書かれたエッセンスって、カウンセリングやコンサルテーションでの課題介入の上手なやり方にも、モロに当てはまるんですよね。
問題を課題に分ける。心理的安全性を確保する。意欲を高める関わりを維持し、主体性がと経験が高まる相互作用の構造を構築する。
もちろん不登校対応や、ビジネスでの人育てなんかにも応用できる、すべての基本がここにあるのでは?と思っています。
10/9(木)赤はな先生と「子どもの心のケアと成長」に向けての対談企画(YouTubeLiveもあります)
【対談企画】赤はな先生と語ろう「子どもの心のケアと成長に向けての関わり」
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!