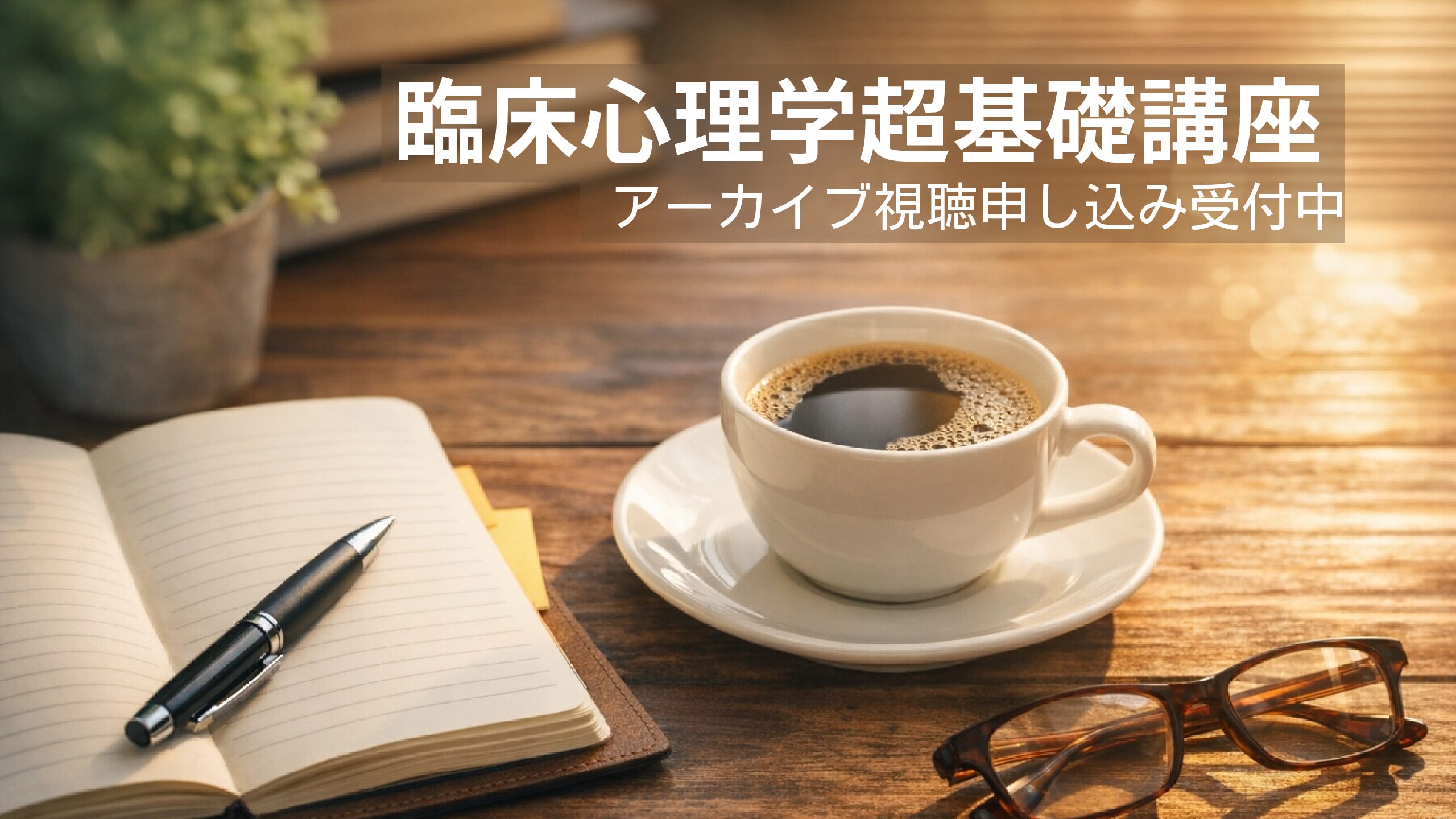不登校支援の現場から考えること その3ー 学校現場の支援者が解決志向にシフトする価値

学校現場における支援では、問題志向ではなく解決志向の考え方を取り入れることが非常に価値があると思われます。
問題志向では、「なぜこの子はこうなったのか?」「原因は何か?」という過去に目を向けがちですが、解決志向では「この子はどうなりたいのか?」「どのように前に進めるか?」という未来に焦点を当てます。
この視点の違いは、支援の方法だけでなく、子ども・保護者・教師の関わり方にも大きな影響を与えます。
解決志向の支援を実践することで、子どもたちがより前向きな自己イメージを持ち、教師や保護者も「何が問題か」ではなく「どうすれば良いか」に意識を向けられるようになります。
目次
Toggle「今ここ」の感情に寄り添うことの大切さ
過去を振り返って、現在の自分を理解することはとても重要なことですが、原因を追求するために自身の問題にフォーカスしすぎてしまい、問題についての周りをぐるぐると考えて出て来れなくなってしまうことがあります。過去を振り返ることが問題志向であるのに対し、現在の感情体験や未来について扱うことは、子どもたちが今を生きる手助けになります。
例えば、家庭訪問の場面でも、私は「今ここでの感情」に寄り添うことを大切にしています。
子どもが「今、自分はダメだな」と思っていると、それだけで活力がなくなり、何をしても楽しめなくなります。
しかし、その場で一緒に感情を受け止めてくれる人がいることで、抱えていた鬱憤が少しずつ解放されていきます。感情を抱えるということは受容と共感、ということだけでなく、その時、その子が関心のあること、コミットしていることについて、自分が肯定的な関心を向けること、一緒に感情を味わう体験をすることが、非常に役に立ちます。
これは意識的にセラピーをしているわけではなくても、結果としてセラピーのような効果を生むのです。そういう意味では、訪問看護や不登校の訪問支援サポートの方が大いに活躍されているのではないかと思いますし、教師であってもそのような関わりができるようになればと願うばかりです。
「どんなふうに変わりたいか?」という問いの力
思考とは、「この人はどんなふうに変わりたいのか?」という問いから生まれるものです。
人は自分の未来を語ることで、現実を少しずつ変えていくことができます。
例えば、不登校の子どもに対して、「なぜ学校に行けないのか?」ではなく、「どんな未来を生きたいと思う?」と問いかけると、子ども自身が自分の未来について考え始めます。
この未来像を、子どもだけでなく、保護者や学校の先生と一緒に共有しながら作っていくことが、学校現場での支援の重要なポイントとなります。
解決志向を取り入れたことで、スクールカウンセラーの仕事はとてもやりやすくなりました。
不登校の原因を特定し、それを取り除くことで解決する場合もありますが、多くの場合、明確な原因があるわけではありません。
「いじめがなくなったら登校できる」わけではなく、いじめが発端となって他の問題が生じ、子どもの関係性が変化していることが多いのです。
だからこそ、未来志向のアプローチが有効なのです。
学校を一旦置いて考えてみる
私は、支援の場で「学校のことは一旦置いといて考えてみよう」という話をよくします。
特に、不登校の子どもにはよく使うフレーズです。
「学校のことは一旦置いといて、どんなことができたら1日がちょっと楽しくなる?」
「学校に行くかどうかは置いといて、20年後はどんな風に生きていたらいい感じ?」
こういう話をしていると、横で聞いている先生が「でも、そのためには学校に行かなきゃな」と言い出すことがあります。
未来のイメージを広げることが目的なのに、「やっぱり学校に行かなきゃ」と現実に引き戻されると、子どもは一気に気持ちが沈んでしまいます。
だからこそ、未来を見据えつつ、その道筋は子ども自身が決めていけばいいというスタンスが大切です。
「あなたは強い子だから、きっと自分で良い方向に進んでいけるよ」というメッセージを伝えながら、その子の良さをしっかり伝えることで、学校に行けない自分を否定しなくても良いと思えるようになります。
すると、話を聞いている先生や保護者も、「そういえば、私も学校をサボったことがあったな」と思い出したり、
「この子が元気ならそれでいいんだよね」と新たな視点を持つことができるようになります。
こうして、子どもの自己イメージが変わると、家族や学校の雰囲気も少しずつ変化していきます。
問題を問題として扱わないことの大切さ
学校では、「間違ったものは間違っている」と評価されがちです。
「良いものは良い」「悪いものは悪い」とジャッジされることが多いため、支援の場でも「この子が問題だ」と決めつけてしまうことがあります。
しかし、問題を問題として扱うことで、実際にその問題が深刻化してしまうことがあります。
これは心理学や社会的実験でも明らかになっています。
「弱者」として扱われることで、人はより弱くなってしまうのです。
だからこそ、学校で支援する際には、「子どもや保護者を支援者の輪に入れる」ことが大切です。
これは、問題を「外在化する」アプローチにもつながります。
問題の外在化で関係が変わる
「彼が問題だ」と言うのではなく、「彼はある困りごとを抱えていて、それに困っている」と言い換えるだけで、支援の方向性が大きく変わります。
例えば、先生が「この子は問題です」と言っていたとしても、
「この子は今、ある困りごとに悩んでいるんですね」と言い換えることで、子どもと問題が切り離されます。
すると、先生も「一緒にこの困りごとをどうにかしよう」と前向きな関わり方ができるようになります。
これはカウンセリングの場でも同じです。
例えば、「私は強迫神経症なんです」と言われたときに、
「あなたのおっしゃられている強迫神経症とは、具体的にどんな行動のことですか?」と質問すると、
「手を何度も洗ってしまう」「壁を触れない」という具体的な行動が出てきます。
そこで、「じゃあ、1日どのくらい手を洗う?」と聞くと、「ご飯の前と外から帰ってきたときで4回くらい」と具体的な回数が見えてきます。
「それ以外の時間はどう?」と聞くと、「そのときは特に気にならない」と答えることもあります。
つまり、「私は強迫神経症」というアイデンティティではなく、「特定の場面で困ることがある」という形に捉え直すことができます。
この違いは非常に大きく、問題を問題として扱わないことで、本人の気持ちがぐっと楽になるのです。
まとめ
解決志向の考え方を取り入れることで、支援の方法が大きく変わります。
・「過去の原因」ではなく「未来の可能性」に目を向ける
・「今ここ」の感情を大切にする
・「問題」として扱わず、「困りごと」として外在化する
このような視点を持つことで、支援の場がより前向きで効果的なものになっていきます。
問題ではなく、解決に目を向けることが、子どもたちの未来を拓く鍵になるのです。
💡 臨床の基礎をじっくり学べるオンライン講座のご案内
臨床心理の世界では、基礎をしっかり身につけることがとても大切です。特に、臨床経験が浅い方や改めて学び直したい方にとって、「基本の考え方」や「実践的な技法」を体系的に学べる場は貴重ですよね。
そこで今回ご紹介するのが、「臨床超基礎講座&解決志向超基礎講座」 です。
この研修プログラムは、臨床心理士・公認心理師・教師・スクールカウンセラー・ソーシャルワーカーを目指す方や、対人支援に関わる方を対象に、基礎からしっかり学べるカリキュラムになっています。
📌 この講座の特徴
✅ 基礎のさらに基礎から学べる ー 傾聴、治療構造、見立て、共感、解決志向など、多彩なテーマを扱います。
✅ 6回シリーズでじっくり学習 ー2025年4月18日より 毎月第3金曜日の21:00〜23:00にオンライン開催。解決志向講座は10月17日スタート。
✅ 実践に活かせる内容 ー すぐに現場で役立つ視点やスキルが身につきます。
詳しい内容やお申し込みについては、こちらからどうぞ👇
https://pro.form-mailer.jp/lp/735d131a326854
興味のある方は、ぜひチェックしてみてください!

オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!