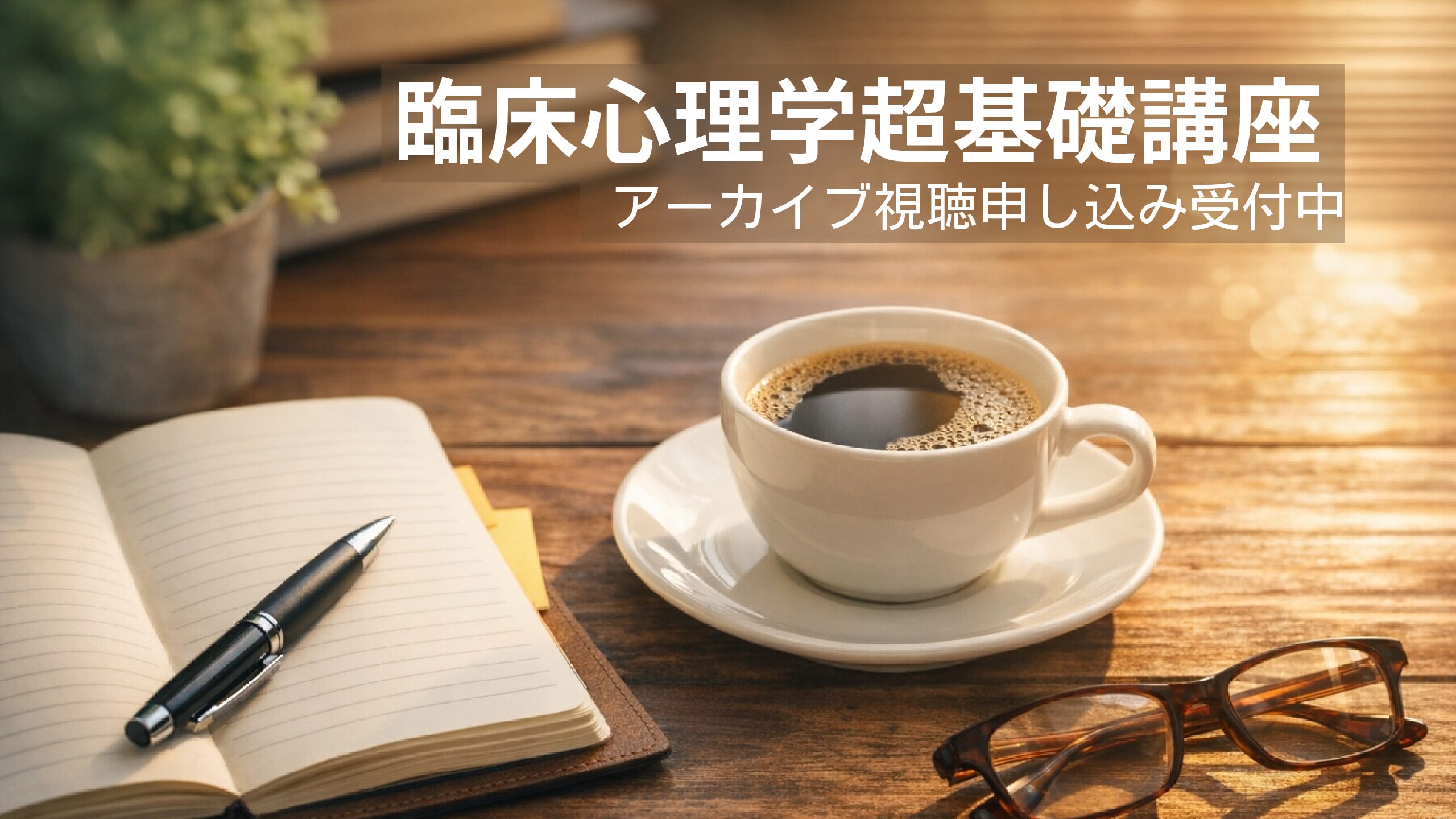不登校対応での最初の目標の立て方について 〜今の状況を地下室ありの三階建てで見てみる〜

不登校対応での最初の目標の立て方について
以前アップしたスクールカウンセラーのゴーリー氏との対談動画なのですが、久々に見てみたら、その内容があまりにも現場感覚に富んでいて実践的だったので、多くの保護者や支援者の方に知ってもらいたいと思い、ブログにまとめてみました。
ゴーリー氏との対談を通じて感じた、不登校の子どもたちと向き合うときに本当に大切にしたい支援のお話をさせてください。
「ご予定はどんな感じ?」から始める会話
私が不登校の子と面談するとき、必ず聞くことがあるんです。
「ご予定はどんな感じ?」
例えば、こんな答えが返ってきたとします。
「もう中学の間はこのまま学校に行かないで、高校から通信制に行けたらいいな」 「来週から学校行きます」 「2年生になったら行けるんじゃないかと思ってる」 「学校と名のつくところには私は行きません」
色んな答えがあるんですよ。そして、どの答えも大切なんです。
目次
Toggleなぜこの質問をするのか
理由は2つあります。
まず一つ目は、「行かない」という選択肢があってもいいよということを伝えるため。多くの大人は無意識に「学校に行くべき」という前提で話しちゃうんです。でも、その前提を一度外してみる。すると子どもは本音を話してくれるようになります。
二つ目は、具体的に未来を想像してもらうため。「一生学校なんて行かない」って言ってた子も、じっくり話していると「さすがにそれは…」って思うことが多いんですよね。そこから「じゃあ最終的にはどうしたいの?」という本当の気持ちを聞いていくんです。
子どもの「今」を3つの段階で理解する
坂本真佐哉先生の「今日から始まるナラティヴ・セラピー 希望をひらく対人援助」(日本評論社)で紹介されているメタファーがすごく役に立つんです。
子どもの状態を建物の階層で考えるとわかりやすいんですよ。
地下2階:学校に行けない+元気もない
一番しんどい状態。エネルギーが完全に枯渇してしまっています。
地下1階:学校に行けない+家では元気
ここが保護者の方には一番理解しにくい状態なんです。 「家では元気にしてるじゃない。だったら学校にも行けるでしょ?」って思っちゃうんですよね。これがきつい。でも違うんです。
地上1階:学校に行っている+元気がある
理想的な状態ですね。
間違えやすい支援の順番
多くの人がやってしまうのが、地下2階から一気に地上を目指すこと。「学校に行けてないし元気もない」状態から、いきなり「学校に行って元気になって」を求めちゃう。
でもこれ、うまくいかないんです。
正しい順番はこうです
地下2階 → 地下1階(まず元気になる)→ 地上
地下1階の段階になると、子ども自身が選択できるようになるんです。「学校に行こうかな」「別の道もあるかな」って、自分で考えられるようになる。これが大事なんです。
「ゲームばかりで…」というお悩みについて
保護者の方からよく聞く相談です。「うちの子、ゲームばかりしていて」って。
でも私、こう考えるんです。
ゲームができるということは、実はすごいことなんですよ。
本当にしんどい時期って、ゲームすらできないんです。楽しいことを楽しめないから。だからゲームをやれているということは、「楽しいことを楽しめる状態にある」ということ。回復の兆しとも言えるんです。
ゲーム時間への向き合い方
私がお母さんたちにお話しするのは、こんなことです。
「今の枠組みは、できるだけ変えないでください」
つまり、急に制限を厳しくしたり、逆に全部自由にしたりしない。大枠は今のままで、質を上げていきましょうと。
例えば:
- ゲームをしている時に、ちょっと一緒にいる時間を増やしてみる
- 子どもが話したがっている時は、じっくり聞く
- 読み聞かせや、子どもがリラックスできる時間を充実させる
そして何より大切なのは、お母さんがゲームをしている子どもを見て「あ、楽しそう」「ちょっとホッとした」って思えること。その気持ちを子どもは敏感に察知するんです。
信頼関係があるからこそ言える言葉
私はよく子どもたちにこう声をかけます。
「君、休むの下手だよね」 「今、ゲーム以外に楽しいことってないんじゃない?」 「でも君はちゃんと元気が出たら、やることやるよね。知ってるよ」
最後の一言が大事なんです。信頼してるよって伝える。でも甘やかすんじゃなくて、ちゃんと「楔は打つ」。このバランスが重要なんです。
「交渉」も大切な練習
ゲーム時間のルールについて親子で話し合う時間、実はこれ、すごく貴重な交渉の練習なんです。
多くの不登校の子って、これまで自分の意見を聞いてもらったり、話し合いで何かが決まったりする経験が少ないんですよね。
だから私は保護者の方にこうお話しします。
「最終的な防衛ラインだけ決めておいて、その中で交渉してみませんか?」
子どもの要求を全部聞くわけじゃない。でも、ある程度は「自分の意見が通った」という経験をしてもらう。これって、自我の再構成にすごく大切なプロセスなんです。
結局、多くの子は「戻っていく」
面白いことに、「学校復帰を前提としない」で支援を続けていても、結果的に多くの子が何らかの形で学校や社会に戻っていくんです。
なぜかって言うと、自分で生きていくために「あ、やっぱり必要だな」って自分で判断するから。これが大事なんです。無理やりじゃなくて、自分の選択として。
私がよく子どもたちと話すのは:
「最終的にはどんな仕事に就きたい?」 「そのために今できることって何かな?」 「もし学校に行くとしたら、どのくらい行けば大丈夫そう?」
こういう具体的な話し合いを通して、子ども自身が将来を描けるようにサポートしていくんです。
大人も面倒なことの前には一息つきたい
考えてみてください。大人だって、面倒な仕事に取りかかる前には「ちょっと一息」つきたくなりますよね。コーヒー飲んだり、スマホ見たり。
子どもだって同じです。むしろ、もっとその時間が必要かもしれません。
目の前で起こっている子どもの「ダラダラ」を、「無駄な時間」と見るのか、「回復に必要な時間」と見るのか。この視点の違いが、子どもとの関係や回復の仕方を大きく変えるんです。
最後に
不登校支援で一番大切なこと。それは回復には段階があるということを理解することです。
- まずは安心安全な環境を整える
- 子どものエネルギー回復を最優先にする
- 元気が出てきたら、一緒に選択肢を考える
- 本人の主体性を大切にしながら将来を描く
急がば回れ。子どもの「今」の状態をちゃんと理解して、その段階に合った関わりをしていく。それが結果的には一番の近道になる場合が非常に多いかと思います。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!