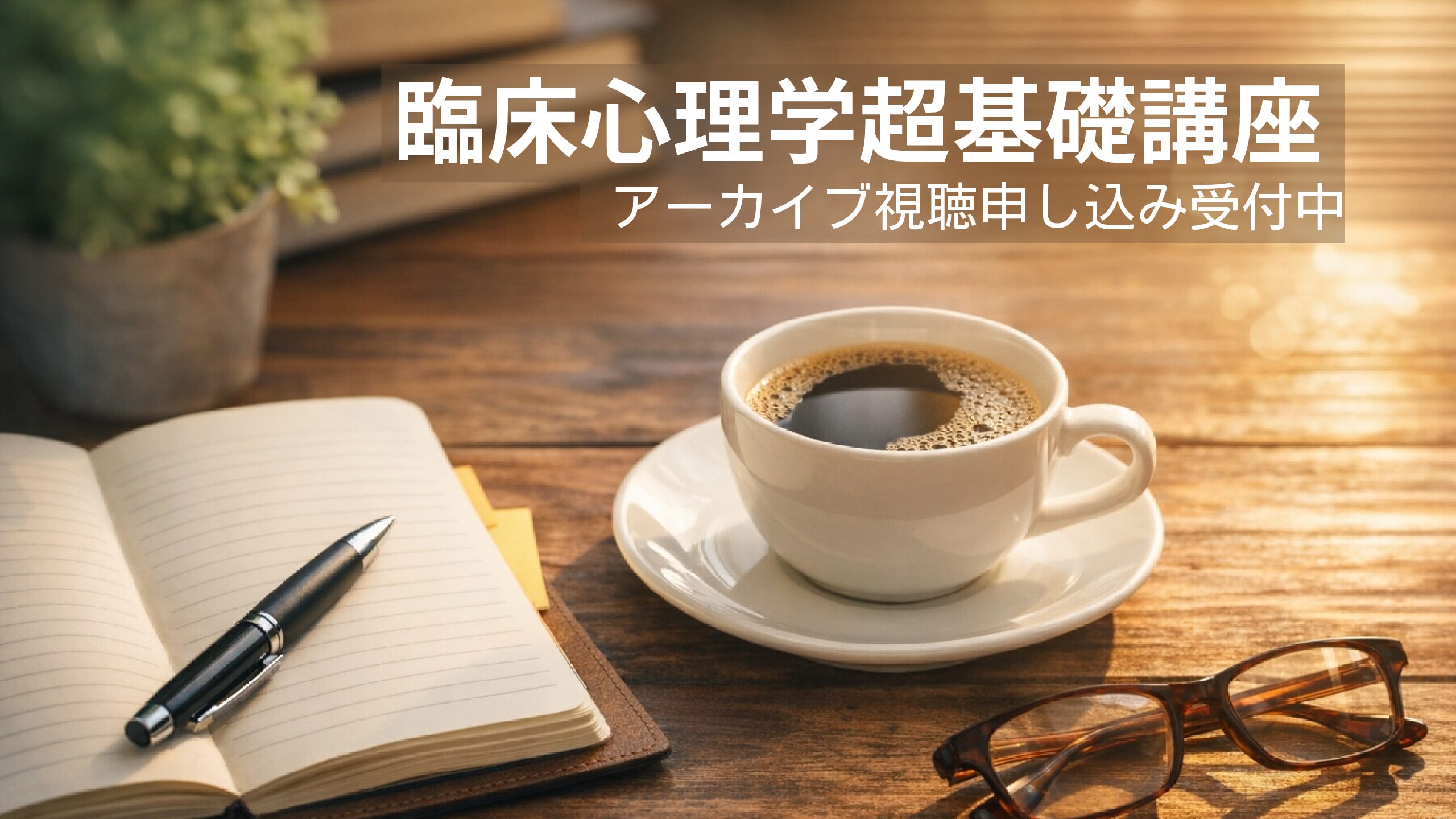スクールカウンセラーのお仕事

目次
Toggleスクールカウンセラーの仕事
私はこれまで、静岡や山梨、名古屋などでスクールカウンセラーとして働いてきました。
一番多いときで、12校ぐらい担当していました。公立の学校ですね。だいたい隔週で訪問して、1回の勤務が6時間のことが多かったです。午前10時から午後4時まで。その中に小学校も高校もあって、午後だけ勤務の高校もありました。3時間だけ。だから、午前は小学校、午後は高校、みたいな日もありました。
やっぱり一番多いのは保護者対応ですね。子どもと直接会うのは、それほど多くありません。もちろん、子どもと会うこともありますけど、数としては保護者の面談の方が多いです。だいたい1回で3人から4人、多いと5人くらい面談していました。1人あたり30分から50分ぐらいで。基本的には担任の先生が話を聞いてほしい保護者の方に声をかけてくれて、「じゃあ会いましょうか」という感じで日程を組みます。
その前に、担任の先生からその子どもの様子を聞いたり、実際に授業をちょっと見せてもらったり、廊下でその子と少し関わってみたりします。短い時間でもその子の様子を自分で見てから、おうちの方とお話をする。やっぱり、担任の先生の話と、保護者の話と、現場で自分の目で見た印象と、それぞれが違っていることもあるので、できるだけ多くの情報を持ってから話をしたいんですよね。
保護者の方の話を聞くと、家庭での困りごとや、学校への不安、担任の先生との関係のこと、きょうだいのこと、いろんな話が出てきます。ときには、話しているうちに涙を流される方もいらっしゃいます。こちらから何か解決策を提示するというよりは、「まずは話すことが大事」と思っている方も多いです。
ただ、担任の先生があまり具体的なプランなく「話してもらうと助かる」という感じで保護者に勧めていることもあって、その場合、保護者の方があまり乗り気じゃないケースもあります。そういうときには、「ひょっとして乗り気でないのでは?どんな経緯で?」と尋ねてみて、来られたこと自体を労うところから入るように心がけています。乗り気ではなくても、実際には困っていることがないわけではない場合が多いので。面談が終わったあとに「話せてよかった」と言ってもらえることが多いですけど、それがどこまで本心かどうかまではわからないですよね。ただ、少しでも気持ちが軽くなってもらえたら、それだけでも意味があると思っています。
それと、子どもとの関わりもいろんな形がありますね。中には、SCが来る日だけ学校に来る、という子もいます。そういう子と会うときは、特に何か話題を用意しているわけではなくて、「来てくれてありがとう」みたいな感じで話します。おしゃべりしたり、カードゲームしたり、一緒に漫画読んだり、そんな感じです。その中で、ちょっとした本音が出てくることもあります。
たとえば、最初はちんまりと言葉少なでいた子供が、来るたびにちょっと図々しくなって、自分のことを話せたり、何か主張ができるようになったり。毎回何か成果が出るわけじゃないですけど、そういうふうに少しずつ関係ができていくのが大事なんじゃないかと思います。
学校との連携
担任の先生との連携もとても大切です。担任の先生もいろんな思いを抱えていて、「この子のことを何とかしたい」と思っている先生が多いです。でも、どう関わればいいかわからない、とか、自分の対応がうまくいっていない気がする、みたいに悩んでいることもあるので、そのあたりを一緒に考える時間もとっています。
もちろん担任の先生に「こういうふうにしてみたらどうですか」と提案することもありますけど、あくまで「担任の子供の成長への願い」を聞いて、そこに向けて「一緒に無理のない関わりの方法を考える」というスタンスです。絶対に上から「こうしたほうがいい」という言い方はしない。SCは専門家という立場ではありますが、学校の中では外部の人間でもあるので、そのバランスが難しいんですよね。あまりでしゃばりすぎてもいけないし、何もしなさすぎても意味がない。
それに、学校によってSCの受け入れ方も違います。すごく協力的な学校もあれば、「とりあえず配置されてるからいる」みたいな感じのところもある。だから、最初の段階で、学校の雰囲気とか、管理職の先生の考え方とかをよく見て、その中で自分がどう動けるかを探っていきます。
学校によって、SCがどの程度関わっていいかのラインが違うんですよね。たとえば、担任の先生から「この子について相談したい」と言われても、学校全体での連携が弱いと、なかなか継続的に関われなかったりします。逆に、教頭先生や教務主任が「この子についてはしっかり見ていこう」という方針を持ってくれていると、SCの関わり方も広がります。
継続的に関わっている子どもについては、SCが来るたびに少しずつ面談したり、校内で会話したりしています。たとえば、「朝登校してこられたけど、教室に入れない」とか、「中休みにちょっと落ち込んでる」みたいなときに、「じゃあ少し話そうか」という流れになります。無理に話を聞き出すのではなくて、まずは関係を作ることが大事だと思っています。
ある学校では、SCがくる日にだけ登校できる子がいました。教室には入れないけど、保健室に来てくれて、「今日は来れた」って言うんです。そういうとき、「すげー頑張ったんじゃん!色々不安だったはずなのに、一体どうやって来れたの?」と伝えるだけでも、その子にとっては意味のある時間になると思うんです。継続的に会うことで、だんだん「今日はこんなことがあった」とか「昨日怒られた」とか、少しずつ話してくれるようになりました。
先生たちとの関係性もすごく大事です。最初は「SCって何をしてくれるのかよくわからない」という感じの先生もいます。でも、何回か話をしていくうちに、「この先生は話をちゃんと聞いてくれるんだ」と思ってもらえると、自然と相談してくれるようになります。最初はちょっとした雑談から入って、少しずつ信頼関係を作っていく、という感じです。
たとえば、「この子、最近授業中にすごく騒ぐんですけど、どうしたらいいですか?」みたいな相談があったとき、「どうしてその子がそうしてるのか、何か思い当たることありますか?」と先生に聞いてみます。すると、「家のことでちょっと問題があるみたいです」とか「前の学年でも似たようなことがあったみたいです」と、少しずつ背景が出てくるんです。
そうやって先生と一緒に考えていく中で、「どんな感じに成長するといいと思われます?」と未来像を設定してみたり「じゃあ、こういう声かけをしてみましょうか」と提案したり、「ここに注目して様子をもう少し見てみましょう」と共有したりします。必ずしもすぐに成果が出るわけじゃないけど、先生の中で「一人で抱え込まなくていいんだ」「いざとなったら相談できる」と思えるだけでも、少し気が楽になるんじゃないかと思っています。
SCの仕事って、直接的な解決というよりは、「関わりをつなぐ」「見立てを共有する」みたいなところが中心になります。たとえば、同じ子どもについて担任の先生と養護教諭とSCがそれぞれ話を聞いている場合、そこで情報が共有されていないと、対応がちぐはぐになってしまうんですよね。だから、できるだけ関係者同士での情報共有を心がけています。
もちろん、守秘義務もあるので、本人や保護者の了承を得ながら話を進める必要があります。でも、「先生たちで連携できると、この子にとっていい環境になるんじゃないか」という視点を持って、うまくつないでいくのもSCの役割だと思っています。
SC自身も、時には無力感を感じることがあります。「何も変わらなかったな」と思うこともあるし、「もっとできたんじゃないか」と思うこともあります。でも、何も言わなかった子が、ある日ぽつりと「ありがとう」と言ってくれたり、「また話したい」と言ってくれたりすると、それだけで続けてよかったな、と思えるんです。
ひとつの学校に長く入っていると、「去年対応していた子が、今年は元気にやってますよ」と先生から聞くこともあります。そういうふうに、少しずつでも子どもが元気になっていく姿を見ると、「ああ、この仕事には意味があるな」と改めて思います。
SCの仕事は、目に見える成果がすぐに出るわけじゃないです。でも、子どもや保護者や先生たちとの関係の中で、小さな変化や気づきを積み重ねていくことが、きっと大きな支援につながっていくと思っています。これからも、そういう丁寧な関わりを大切にしていきたいと思います。
📢 心理臨床超基礎講座のご案内
この「協働の7原則」でお話しした内容は、私が開催している心理臨床超基礎講座のテーマとも深く関係しています。
現場で役立つ臨床心理の基本を、具体的事例とともに解説するオンライン講座です。
次回開催予定
第5回 心理臨床超基礎講座
テーマ:理解を伝える(助言とコンサルテーションについて)
日時:2025年8月15日(金)21:00〜23:00
形式:Zoomオンライン開催
※終了後には自由参加のアフターミーティングがあります。
参加者の方からは、
「ただの知識ではなく現場で使える」
「今までの自分の臨床を振り返って、自分が何をしようとしていたのか理解することができた」
「協働のポイントが腑に落ちた」
といった声をいただいています。
👉 詳細・お申し込みはこちら
心理臨床超基礎講座の詳細・お申し込みページ

オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!